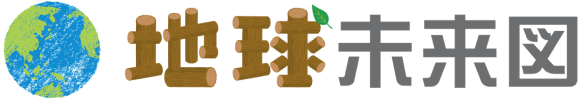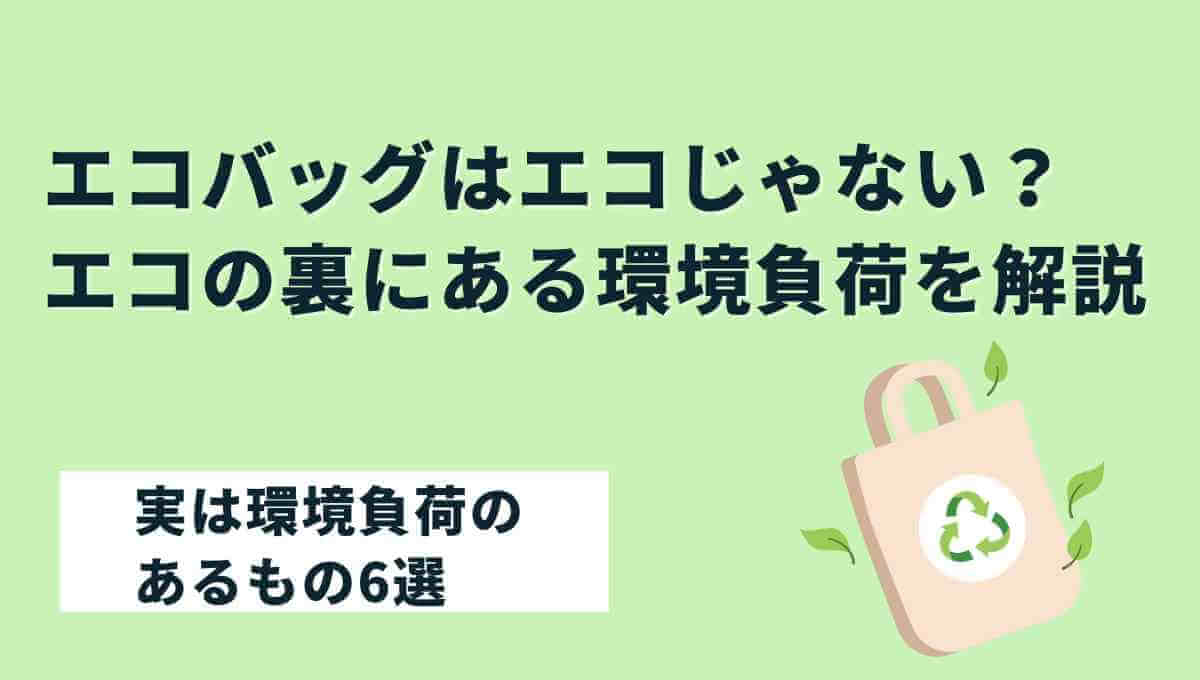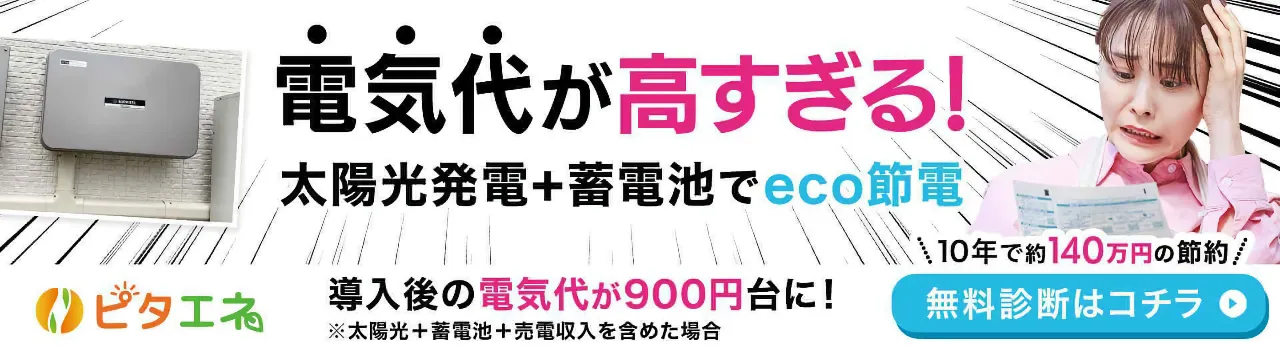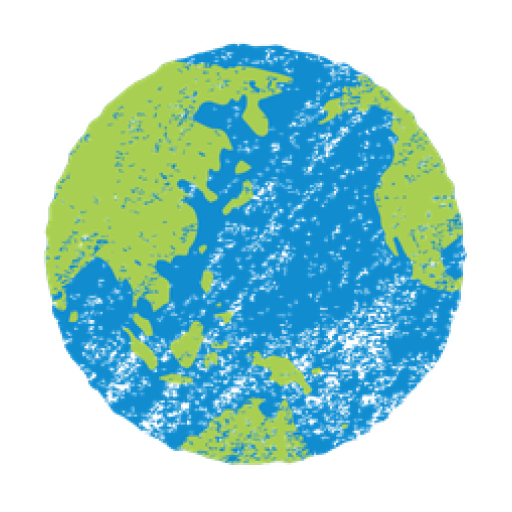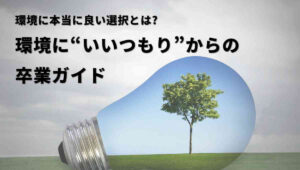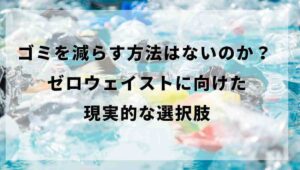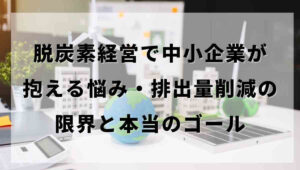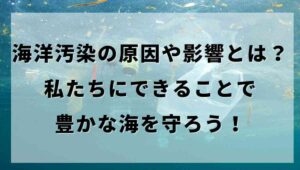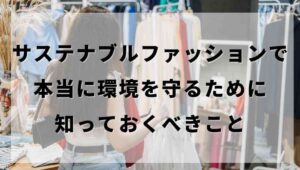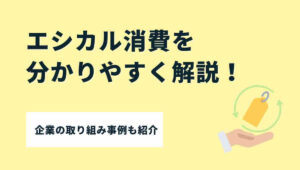プラスチック製レジ袋の有料化が始まり、私たちは日々の買い物にエコバッグを持つことが当たり前の選択肢となりました。CO2排出量やプラスチックごみの削減が重要視される中、「エコバッグは本当にエコなの?」と疑問を感じたことはありませんか?
実は「エコ」という言葉の裏には、企業が見せかけだけの環境配慮をアピールするグリーンウォッシュの側面が隠れていることがあります。この記事では、一見エコに見える製品に潜む環境負荷について根拠のある事例を6つ紹介します。
この記事は企業や個人の取り組みを批判するためのものではありません。この記事の目的は、環境のために良かれと思って選んだ選択肢が別の課題を抱えていることを知ることで、より深く本質的な環境問題を考えるきっかけを提供することです。
表面的なエコのイメージに惑わされず、本当に環境に良い選択をするためのヒントを一緒に見つけていきましょう。
エコバッグの誤解
エコバッグは、プラスチック製レジ袋の削減に貢献する「環境に優しいアイテム」として広く認識されています。 しかし、エコバックの製造方法や素材、使用回数などによっては、レジ袋よりも環境に負荷をかけてしまうことがあるのです。
ここでは私たちが普段使っている綿素材と化学繊維素材ののエコバッグそれぞれに、どのような問題があるのかを紹介します。
①綿素材のエコバッグ
綿素材のエコバッグは、自然由来の素材でできているためエコなイメージが強いですが、その製造過程では大量の水・農薬・エネルギーを使用しており、多くの環境負荷がかかっています。
綿1kgを生産するには、約10,000〜20,000リットルの水が必要であるといわれています。トートバッグ1枚(綿約150〜200g)あたり、1,500〜4,000リットルの水が使われる計算です。
また、世界全体で使用される殺虫剤の約16%、農薬の約7%が綿花栽培に使われているという報告もあります。これらの環境負荷を考慮すると、数十回程度エコバックを繰り返し利用するだけでは環境に優しいとはいえないでしょう。
2018年にデンマーク環境保護庁により公開されたデータによると、綿素材のエコバックをレジ袋の代替として使うには最低でも7,100回使用しなければレジ袋よりも環境負荷が上回ってしまうと示されています。オーガニックコットンの場合は20,000回もの再利用が必要ともいわれています。(参照1)
参照1:Danish Environmental Protection Agency
②化学繊維のエコバッグ
綿に比べると石油由来(プラスチック、ビニール)のバックは製造時や輸送時の環境負荷は軽くなります。先述したデンマーク環境保護庁のデータでは、プラスチックの一種であるポリエステル製のエコバックは最低35回使用すればレジ袋よりもエコになります。
そのため、綿素材のエコバックを利用するよりも、プラスチック製のバッグや少ししっかりしたタイプの繰り返し使える袋をぼろぼろになるまで使うほうが環境にはいいといえるでしょう。
ただし、プラスチックは廃棄の際に自然に還らない(自然環境で分解されない)ため、不適切に廃棄されると環境汚染につながる可能性があります。
 地球未来図
地球未来図エコバックはノベルティとして配布されたり、ファッションの一部としてとらえられることあり、必要以上に消費の助長につながっているケースがあるのではないかいう専門家の意見もあります
エコバックを環境に最もよい形で活用するのなら、必要な場面で長期間使える1枚のエコバックを使い続けることが望ましいでしょう。
合わせて読みたい記事:2025年に知りたいプラスチック削減の取り組み・日本、海外の具体事例
紙ストローの誤解
紙ストローはプラスチック製ストローの代替品として普及していますが、製造時に多くの水とエネルギーを要し、プラスチック製よりも環境負荷を増大する可能性があります。
2022年にアメリカで発表された研究結果によると、8つの環境負荷に関するカテゴリーを分析し独自の指数(複合相対環境影響指数)を求めたところ、各ストローの数値は以下のとおりになりました。(参照2)
| 紙ストロー | 使用後に埋め立てる場合:5.1 使用後に焼却する場合:4.9 |
|---|---|
| プラスチックストロー(ポリプロピレン製) | 使用後に埋め立てる場合:2.4 使用後に焼却する場合:3.2 |
数値が高いほど環境負荷が大きくなるため、使用後にリサイクルしない場合はライフサイクル全体でプラスチックストローよりも紙ストローのほうが環境負荷が高くなってしまいます。
また、紙ストローはリサイクルすることが難しく、ほとんどが燃えるごみとして処理されているのが現状です。使い捨てをすることがそもそも環境に悪いため、リユース可能なストローを使用する、不要な場面では使わない選択をすることが必要です。
外食産業ではストローがサービスとして定着していますが、その意識も将来変わる可能性があるでしょう。
参照2:NLM
合わせて読みたい記事:グリーンウォッシュの実態とこれからー“サステナブル”の裏に潜む罠を知る
バイオプラスチックの誤解
テイクアウト用の容器やレジ袋などに使われているバイオプラスチックは植物由来で分解されるというイメージから、環境に優しい素材と思われがちですが、必ずしも「自然に還る」ことを意味しません。
バイオプラスチックとは、植物などの再生可能な資源を原料としたバイオマスプラスチックと微生物により自然に分解される生分解性プラスチックの総称です。植物由来のバイオプラスチックでも一般的なプラスチックと同様に自然界では分解されないタイプも存在します。
また、生分解性プラスチックでもただ土に埋めただけでは分解されません。特定の温度や湿度、微生物のいる環境下でしか分解されず、現状ではほとんど焼却処分されています。
そのため、「自然に還る」という誤解からポイ捨てや適切な分別の軽視につながらないよう注意しなくてはなりません。成分表示を確認し、自治体の処理ルールに合わせて適切に廃棄・分別する必要があります。また、テイクアウト容器の利用を最低限にするなど、消費自体を減らすことも大切です。
近年、より自然分解しやすい次世代のバイオプラスチック「PHA(ポリヒドロキシアルカノエート)」が注目されています。PHAは微生物が作り出すポリエステル樹脂の一種で、人間の体内でも分解されます。
容器包材だけでなく医療においても活用が期待されていますが、価格が高く大量生産が難しいという課題もあり、さらなる研究・開発が必要です。低温でも分解しやすい生分解プラスチックの研究・開発を進めている企業もあり、今後のバイオプラスチックの動向には期待が持てる側面もみられます。
合わせて読みたい記事:ネイチャーポジティブの国内・海外取り組み事例6選
バイオマス発電の誤解
再生可能エネルギーを使うバイオマス発電は環境にやさしいイメージがありますが、燃料の調達方法によっては環境負荷をかけてしまう可能性があります。
日本においては固定価格買取制度(FIT)とフィード・イン・プレミアム(FIP)制度で認定されているバイオマス発電の9割弱が、輸入バイオマスを主な燃料としています。木質のバイオマスを活用している発電所が多く、海外からの輸入に依存しているのが現状です。(参照3)
バイオマス発電の需要が高まっていることもあり、木質ペレットの輸入量は2023年の581万トンから2024年には638万トンへと増加しています。(参照4)
海外から大量の木質ペレットを輸入する場合、輸送時に多くのCO₂が排出されます。資源エネルギー庁は輸入木質ペレットの輸送工程において、9,000km(おおよそ日本~アメリカ)の海上輸送をすると1MJあたり2.78g(船の種類によっては4.30g)のCO2を排出すると示しています。(参照5)
輸入量が増加すると間接的にCO2排出量を増やすことになるため、国内循環型資源で行わなければ再生可能エネルギーとはいいきれないでしょう。地産地消の木材や廃材を利用した小規模分散型のバイオマス発電へと見直す必要があります。
参照3:NPO法人 バイオマス産業社会ネットワーク
参照4:NPO法人 バイオマス産業社会ネットワーク
参照5:資源エネルギー庁
合わせて読みたい記事:再生可能エネルギー国内・海外企業、自治体の取り組み事例10選
電動キックボードの誤解
シェア型の電動キックボードは脱炭素の象徴として導入が進んでいますが、製造から廃棄までのライフサイクルを考慮すると必ずしもエコとは言い切れません。電動キックボードのバッテリーに使われているリチウムイオン電池を製造する際に大量のエネルギーを消費します。
電動キックボードのバッテリーの寿命は、2~3年ほどといわれており定期的な交換が必要です。使用頻度や充電方法によってはさらに短くなるケースもあります。(参照6)
廃棄する際のリサイクルが課題にもなっており、不適切に廃棄されると有害物質が環境に流出するリスクも無視できません。
バッテリー回収のインフラ不足や放置・故障による使い捨てなどを考えると、そこまでエコとはいえないのが現状です。車やバイクを使うよりも走行中のCO2排出量は減らせるものの、徒歩や自転車を選択すれば済むケースも多いでしょう。
バッテリーが環境に与える悪影響を考慮して徒歩や自転車、公共交通の利用を優先し、電動モビリティは補完手段として限定的に使うのが望ましいといえます。
参照6:glafit
合わせて読みたい記事:グリーントランスフォーメーション(GX)事例|日本と海外の最新取り組みを紹介
オンライン化・クラウド利用の誤解
クラウドサービスの利用やオンライン化は「紙を使わないエコ」として推奨されがちですが、サーバー稼働や冷却に膨大な電力を消費しています。
無制限の写真・動画保存、使い捨て的なアプリ使用、さらにAIの台頭で電力が飛躍的に必要になってきているのが現状です。国際エネルギー機関(IEA)は、AIを扱うデータセンターの電力需要は2024年と比較して2030年までに2倍以上に増加すると予想しています。(参照7)
また、一般的なAI向けのデータセンターは1年間に10万世帯分の電力を消費すると示しており、将来的にはさらに多くのエネルギーが必要になるでしょう。紙に戻せばいいということではありませんが、データになったからといってエコだと過信できません。
ここまでに紹介してきた「長年環境によいと考えられてきた活動」にもマイナス面があったよう、IT分野と環境保護の関係においては、これからより大きな問題が見つかる可能性があります。
今からでもできる対策として、データ使用量を意識し長期間使わないファイルを削除する、再生可能エネルギー利用したデータセンターを選ぶなどのデジタル環境における環境負荷を意識した対策も重要になります。
参照7:IEA
合わせて読みたい記事:生成AIに伴う環境負荷とは?データセンター増加で電力を大量消費
なぜ“エコの誤解”は広がったのか



さまざまなエコの取り組みに誤解があることは理解できたけど、どうしてこのようなエコの誤解が広がったのかな?



企業のマーケティングやメディアの報道、そして消費者自身の認識のギャップが原因として挙げられます。
本来、環境にいい取り組みかは単純に判断できることではなく、継続した調査により、「数値をみながら本当に環境に効果があるのか」具体的にを検証する必要がありましたが、マーケティング目的でも利用され、中身よりもうわべの活動やキャッチコピーが一気に広まってしまった背景があります



紙ストローはプラスチックよりも環境にやさしい、エコバックを持てば環境に貢献できるみたいな宣伝のことね



そうです。また、メディアや社会が分かりやすさを重視して「脱プラ」「SDGs元年」などの単純化したイメージをトレンドにしてしまったことにも責任があります



キャッチコピーやイメージを鵜呑みにしてしまった私たち消費者にも責任があるわね



そのような考え方もありますね。ただ、エコ活動自体は悪いことではなく、環境に配慮したいというたくさんの人々の善意や環境問題に対する危機感から生まれた素晴らしい行動です。
その思いを無駄にしないよう、表面的な情報だけでなく具体的な活動内容や数値目標などを確認することが大切です
合わせて読みたい記事:サーキュラーエコノミーの成功事例|日本と海外の最新取り組み6選
まとめ:“エコだから”ではなく“どうエコか”を考える
エコバッグや紙ストローなど、一見エコに見える製品にも隠れた環境負荷が潜んでいます。これらの製品がすべて悪いわけではありませんが、製造から廃棄までのライフサイクル全体で考えると、決して環境負荷がゼロではないことが分かります。
エコかどうかを考える際は、ライフサイクル全体で環境負荷を減らせるかの視点が重要です。企業のマーケティングや簡略化された情報に惑わされず、製品がどのように作られどのように処分されるのかを知る必要があります。
さらに踏み込んで考えれば、エコなものであっても消費を続ければ環境に負荷を与えてしまいます。持ちすぎないことや使わないことも選択肢に加え、無意識の消費行動そのものを見直すことも大切です。
私たち「地球未来図」では、再エネの知識をわかりやすく伝えるだけでなく、実際に行動に移すための選択肢も紹介しています。
運営元のレオフォースは、太陽光発電を生活に取り入れる人を増やすために、ピタエネという太陽光発電設置の相談や代理店サービスも展開しています。
「環境のために、まず何か始めたい」
そんな方は、ぜひこちらの特集【ピタエネのひみつ】もご覧ください。
※本記事は「ピタエネ」を紹介するPRコンテンツを含みます