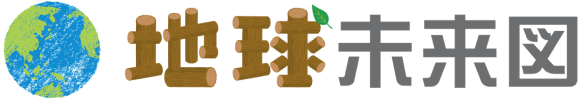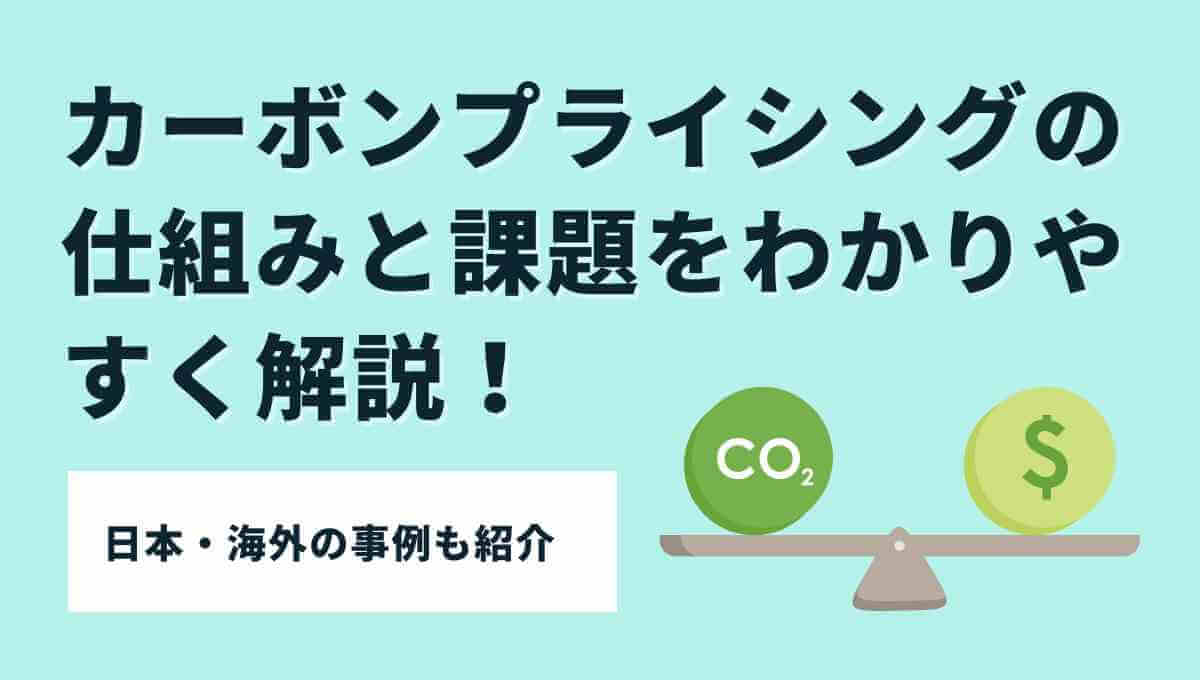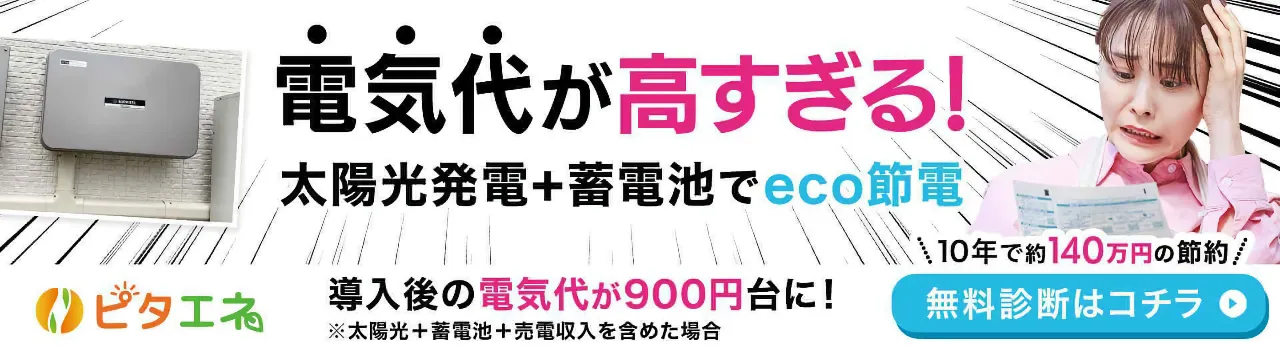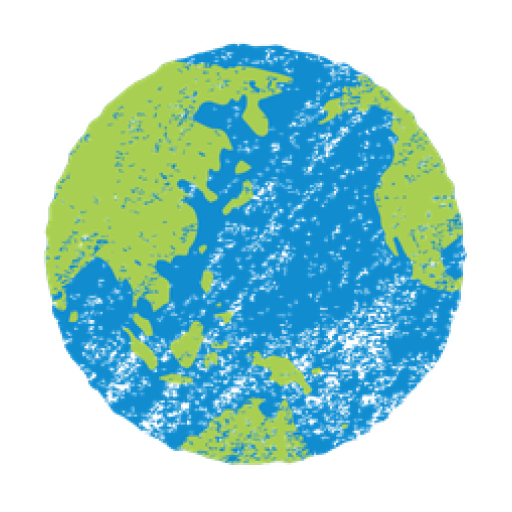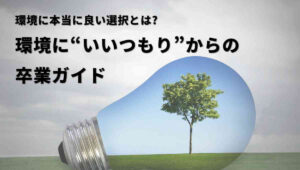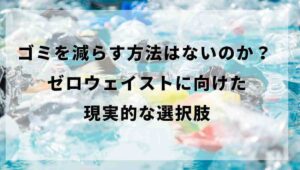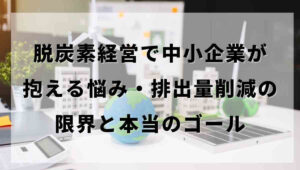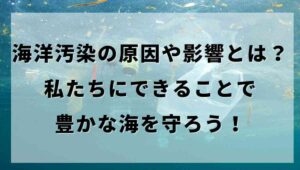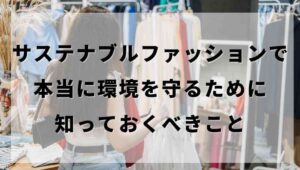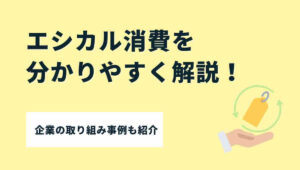近年、脱炭素社会の実現に向けてカーボンプライシングを導入する国が増えています。カーボンプライシングとはCO2の排出にコストを課すことで、経済と環境の両立を目指す重要な制度です。
この記事ではカーボンプライシングの基本的な仕組みから、世界や日本の現状、そして私たちの暮らしや企業に与える影響までを専門知識がない方にも分かりやすく解説します。
脱炭素社会の実現に向けた自分や企業、そして社会全体のアクションを考える際の参考にしてください。
カーボンプライシングを理解する
カーボンプライシングとは、CO2(二酸化炭素)の排出量に価格をつけ、企業や個人にCO2排出を減らす行動を促す政策手法です。CO2排出量に応じて金銭的な負担を求めます。
カーボンプライシングの代表例として挙げられるのが、炭素税と排出量取引制度(ETS)です。炭素税は、燃料や電気を使用して排出したCO2に対して課税する制度です。排出量が増えるほど、多くの税金を納付しなくてはなりません。
また、排出量取引制度は企業ごとにCO2排出量の上限を決め、排出枠を売買できるようにする制度です。上限を超えてしまった企業は、上限を下回る企業から排出枠を購入する必要があります。
このようにカーボンスプライシングはCO2排出量を企業にとってのコストにするため、排出量を削減した企業は環境に貢献できるだけでなく経済的なメリットも受けられるようになります。
 地球未来図
地球未来図カーボンスプライシングを理解するにあたって、知っておきたい用語を以下の表にまとめましたので参考にしてください
| 用語 | 概要 |
|---|---|
| 炭素税 | 燃料や電気を使用して排出したCO2に対して課税される税金 |
| 排出量取引制度(ETS) | 企業ごとにCO2排出量の上限を決め、排出枠を売買できるようにする制度 |
| カーボンオフセット | 森林保護や再生可能エネルギー事業への投資などの温室効果ガスを削減する活動をして、自身が排出した温室効果ガスの埋め合わせをする取り組み |
| カーボンフットプリント | 製品・サービスの原材料調達から廃棄、リサイクルまでのライフサイクル全体で排出した温室効果ガスをCO2排出量に換算した値 |
合わせて読みたい記事:脱炭素社会とは? 簡単・分かりやすい用語解説|地球環境をどう守る?
カーボンプライシングと炭素クレジットとの違い
カーボンプライシングと炭素クレジットはどちらもCO2排出量の削減に関わる制度ですが、その仕組みには明確な違いがあります。カーボンプライシングは、CO2排出量に税金や罰金をかけることで、企業に排出量の削減を促す政策です。CO2の排出そのものが企業のコストになります。
一方で、炭素クレジットはCO2削減に貢献した企業やプロジェクトが、その削減量を「クレジット」という形で認証・発行してもらい、市場で売買できるようにする仕組みです。CO2の削減量が企業への報酬になります。
排出量取引制度でこのクレジットが取引されることもあり、炭素クレジットはカーボンプライシングの一部ともいえます。
合わせて読みたい記事:カーボンニュートラルの具体例13選|国内・海外の最新事例を紹介
カーボンプライシングは今、どういう状況なのか
現在、カーボンプライシングは世界中で導入が進んでおり、各国の経済活動に影響を与え始めています。日本においても、具体的な導入に向けた議論が活発に行われている状況です。
世界の動向を見ると、すでに多くの国や地域で炭素税や排出量取引制度が導入されています。世界銀行が発表した2024年版「カーボンプライシングの現状と傾向」によると、2024年4月時点において世界で導入されているカーボンプライシングの施策は75件でした。(参照1)
また、炭素税と排出量取引制度による政府の収入は世界全体で1,040億ドルでした。初めて1,000億円を超えており、カーボンプライシングが普及しつつあることがわかります。
参照1:独立行政法人日本貿易振興機構
合わせて読みたい記事:SDGsと脱炭素は関係あるの?それぞれの意味や役割を紹介
日本政府の動き
海外に比べ遅れてはいるものの、日本でもカーボンプライシングの導入が進んでいます。2012年には「地球温暖化対策のための税」が導入され、化石燃料の利用に対して税金が課されました。段階的に税率が引き上げられ、現在はCO2排出量1トンごとに289円となっています。(参照2)
また、2023年に成立したGX(グリーントランスフォーメーション)推進法のもと、化石燃料賦課金と排出量取引制度の導入が予定されています。
化石燃料賦課金とは化石燃料の輸入事業者等に対して課される金銭的負担です。化石燃料に由来するCO2排出量に応じて負担する金額が決まります。化石燃料賦課金は2028年から開始する予定です。(参照3)
排出量取引制度は、日本のCO2排出量の5割超を占める企業群が参画したGXリーグで試験的に導入されています。GXリーグは経済産業省によって設立された枠組みで、カーボンニュートラルに向けて積極的な挑戦を行い、国際ビジネスで勝てる企業群が参画しています。(参照4)
2023年よりGXリーグのもとで排出量取引「GX-ETS」を実施しており、データを集めたうえで2026年から本格稼働する予定です。
合わせて読みたい記事:グリーントランスフォーメーション(GX)事例|日本と海外の最新取り組みを紹介
国内事例
国内では日本政府だけでなく自治体でも独自のカーボンスプライシングを導入しており、企業がインターナルカーボンプライシング(企業独自のカーボンスプライシング)に取り組む事例も出てきています。ここでは国内事例を2つ紹介します。
埼玉県
埼玉県は、独自の排出量取引制度である「目標設定型排出量取引制度」を導入しています。目標設定型排出量取引制度とは、CO2を大量に排出する大規模な事業所に削減目標の設定と実施状況の報告を義務付ける制度です。(参照5)
エネルギー(化石燃料や電気など)使用量が原油換算で1,500kLを超える事業者が主な対象となります。埼玉県はこの制度を2011年から導入しており、制度対象の事業所全体として目標削減率を上回る実績をあげています。
参照5:埼玉県
HITACHI
日本最大の総合電機メーカーであるHITACHIは、2019年度から「日立インターナルカーボンプライシング(HICP)」を導入しています。(参照6)
社内の炭素価格をCO2排出量1トンあたり14,000円と設定し、設備投資によるCO2 削減量の効果やエネルギー削減量の効果を金額換算することで、各事業所にCO2排出量削減を促しています。
この制度により脱炭素設備への投資が活性化し、2023年度では4,302トンのCO2排出量削減を実現しました。HITACHIは今後もHICPを活用してCO2排出量の削減をさらに進めていく予定です。
参照6:HITACHI
合わせて読みたい記事:サーキュラーエコノミーの成功事例|日本と海外の最新取り組み6選
海外の動向と事例
海外では本格的なカーボンスプライシングを導入している国が多くあります。ここでは3つの海外事例を紹介します。
スウェーデン
スウェーデンは1991年に炭素税を導入して以来段階的に税率を引き上げており、2017年時点で世界最高水準であるCO2排出量1トンあたり119ユーロ(1トンあたり約15,000円以上)の税金を課しています。(参照7)
同時に法人税を大幅に減税することで、CO2排出量の削減とGDP成長の両立を達成しているのも特徴です。2023年時点で、カーボンスプライシングの対象となっている温室効果ガスは国全体の約70%となっており、制度が広く普及されています。(参照8)
EU加盟国全体(EU-ETS)
2005年から開始されたEU加盟国全体で運用されている「EU排出量取引制度(EU-ETS)」は、世界最大規模のカーボンプライシングです。炭素価格は市場変動制ですが、2022年にはCO2排出量1トンあたり90〜100ユーロに達しています。(参照9)
EU-ETSは発電、製造、航空などの産業に適用されており、CO2排出量の上限が設けられています。上限を超えた際には排出枠を購入しないと、超過排出量1トンごとに100ユーロの罰金を支払わなくてはなりません。
2027年には家庭で使う燃料や自動車燃料にも適用する排出量取引制度「ETS 2」が開始される予定です。
参照9:EURO
韓国
韓国は、アジアで初めて全国規模の排出量取引制度(K-ETS)を導入した国です。2015年に制度を開始し、CO2排出量が多い約600の企業を対象に、脱炭素への行動を促してきました。(参照10)
2025年時点では、電力や工業などの各セクターにおいて主要なCO2排出事業者816社を対象としています。炭素価格は10ドル前後と他の国と比べて安価ですが、制度設計を継続的に強化しています。(参照11)
合わせて読みたい記事:ネイチャーポジティブの国内・海外取り組み事例6選
カーボンプライシングの生活や企業への影響
カーボンプライシングが導入されると、私たちの日常生活や企業の経営戦略に大きな影響を与えます。ここでは、カーボンプライシングが私たちの生活や企業に具体的にどのような変化をもたらすのか、2つの側面から解説します。
電気代・ガソリン代の変化
カーボンプライシングは、私たちの生活に身近な電気代やガソリン代に影響を与える可能性があります。電力会社や石油企業が、CO2排出量に応じて負担したコストが電気代やガソリン代に転換されるからです。
2024年時点では、日本で全国的な炭素税や排出量取引制度(ETS)は本格的に導入されておらず、電気代やガソリン代に直接的なコストは大きく反映されていません。
ただし、国のGX推進法にもとづき、2026年以降に化石燃料賦課金や排出量取引制度(GX-ETS)の導入が予定されています。経済産業省などの制度設計案のひとつに、CO2排出量1トンあたり数千〜1万円前後の炭素価格があります。(参照12)
その場合、電気代は1〜2割前後上昇し、ガソリン代は1リットルあたり数円単位の上乗せが起こる可能性があるでしょう。
参照12:環境省
企業の経営や消費者行動の変化
カーボンプライシングは、企業の経営戦略や私たちの消費行動にも大きな変化をもたらします。CO2排出量にコストが課されることで、企業も私たち消費者もより環境に配慮した選択をせざるを得なくなるからです。
CO2排出量を減らすことがコスト削減に直結するため、企業は省エネ設備の導入や再生可能エネルギーへの切り替え、生産プロセスの見直しを積極的に進めるでしょう。その結果、環境に優しい製品やサービスがより多く市場に出回るようになります。
私たちは環境配慮型の製品を「少し高くても価値がある」と評価し、選択するようになるかもしれません。企業や消費者の環境意識が向上するのはいいことですが、今と同じ生活はできなくなる可能性があります。
合わせて読みたい記事:サステナブルファイナンスの実情・“本当”に環境に優しい取り組みとは?
カーボンプライシングへの反対意見
カーボンプライシングは脱炭素社会の実現に向けた有効な手段として期待されていますが、企業や消費者に与える影響を懸念した反対意見もあがっています。ここでは、カーボンプライシングに対して寄せられる主な反対意見を2つ紹介します。
「制度が機能していないのでは?」という声
カーボンプライシングには「制度が機能していないのでは?」という、制度の実効性に対する疑問の声があります。制度設計が不十分だと、企業や消費者の行動が変わらず、排出削減につながらないからです。
たとえば、炭素価格がCO2排出量1トンあたり数百円程度では、排出削減にかける費用より支払いを選ぶほうが企業にとって安上がりになります。また、現状の排出量取引制度は大企業や特定産業に偏っており、国全体の削減には不十分です。
単に制度を導入するだけでなく、市場の動向や排出削減目標を考慮した、適切な価格設定や排出枠の調整を行う必要があります。
合わせて読みたい記事:グリーンウォッシュの実態とこれからー“サステナブル”の裏に潜む罠を知る
貧困層・地方・中小事業者への影響
カーボンプライシングは、経済的に弱い立場にある人や特定の地域、中小事業者への負担が大きくなるとの意見もあります。CO2排出量にコストをかけると、生活や経営を圧迫する可能性があるからです。
たとえば、電気代やガソリン代などが値上がりすると、低所得者層にとっては生活費の負担が増加してしまいます。また、大企業に比べて脱炭素のための設備投資が難しい中小事業者も、コスト増を転嫁できず、経営が厳しくなるリスクがあります。
都市部と地方での交通手段の違いや断熱住宅へのアクセス格差など、地域間の不平等も考えなくてはなりません。環境への配慮は重要ですが、実質的に取り残される人を作ってしまうという大きな問題を解決する必要があります。
本当に“炭素に値段をつける”社会は実現できるのか?
カーボンプライシングはCO2排出にコストを課すことで、脱炭素への行動を促す重要な政策です。世界中で導入が進んでおり、日本でも本格的な運用が始まろうとしています。
カーボンプライシングの導入が進むことで、CO2排出量が削減され脱炭素社会の実現に近づけます。一方で、電気代やガソリン代が値上がりしたり企業の経営戦略や消費者行動が変化したりする可能性があります。
貧困層への影響や制度の設計上の課題など、解決すべき問題はまだ多く残っているのが現状です。「炭素に値段をつける社会」が本当に実現できるかどうかは、これらの課題に向き合い解決策を見出せるかにかかっています。
そのためには、私たち一人ひとりがカーボンプライシングの仕組みを、まず知っておくことが役立ちます。そして、まだ課題も残る中で、この制度が社会にどう貢献していくのか見定め、アップデートしていく必要があるでしょう。
私たち「地球未来図」では、脱炭素社会や再生可能エネルギーに関する知識をわかりやすく伝えるだけでなく、実際に行動に移すための選択肢も紹介しています。
運営元のレオフォースは、太陽光発電を生活に取り入れる人を増やすために、ピタエネという太陽光発電設置の相談や代理店サービスも展開しています。
「環境のために、まず何か始めたい」
そんな方は、ぜひこちらの特集【ピタエネのひみつ】もご覧ください。
※本記事は「ピタエネ」を紹介するPRコンテンツを含みます。