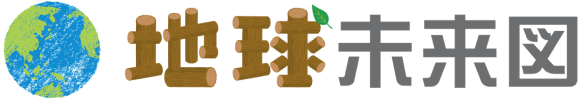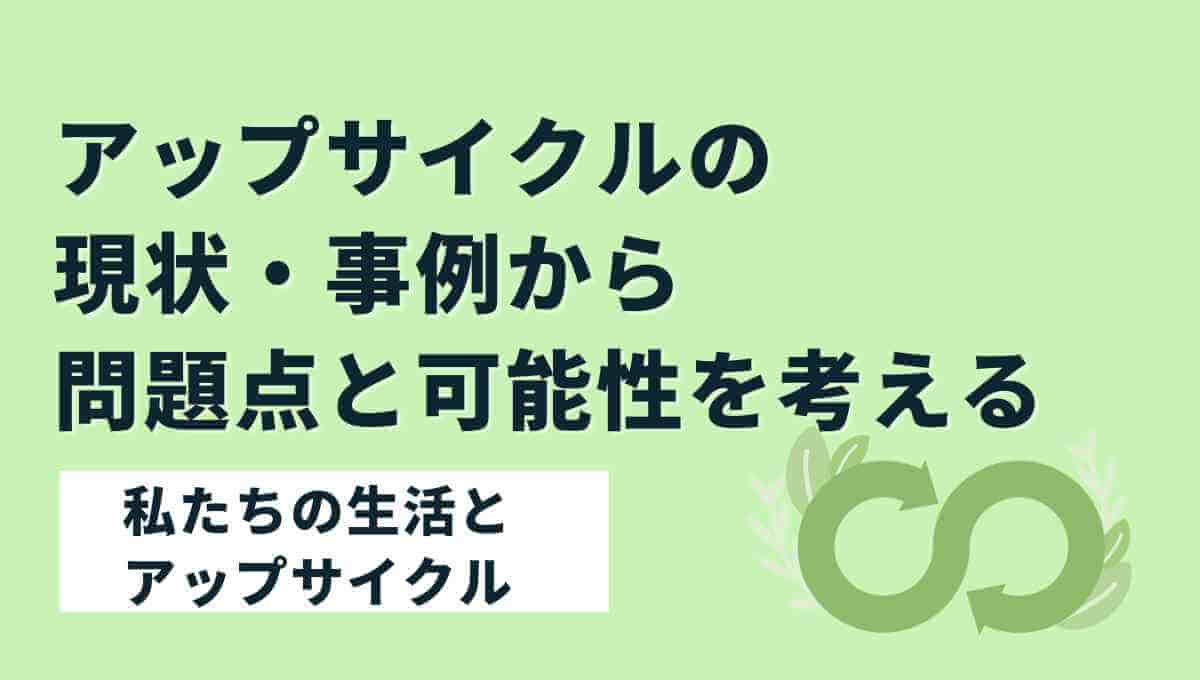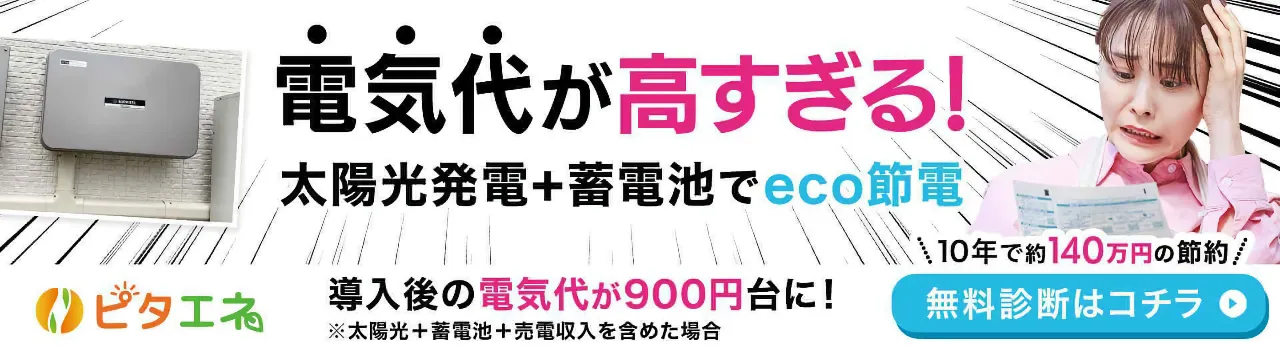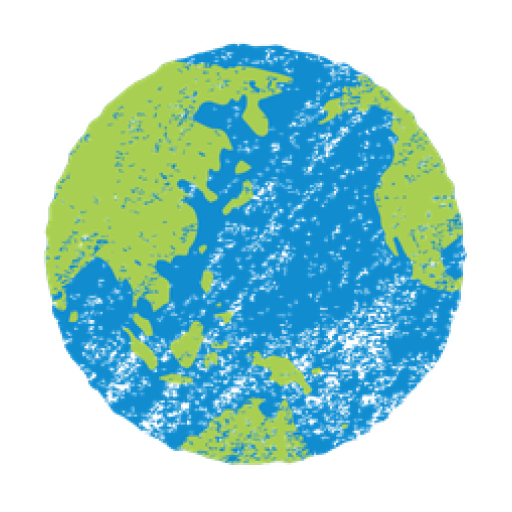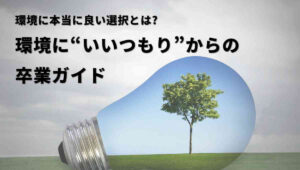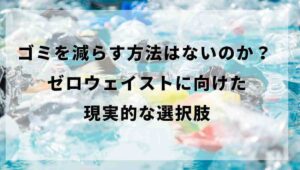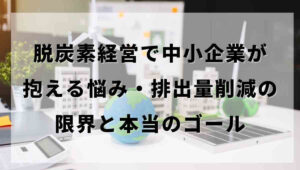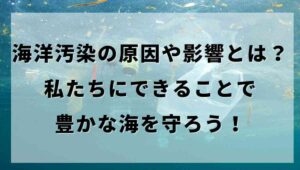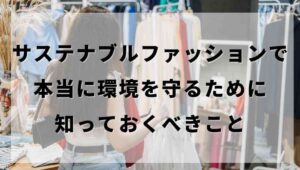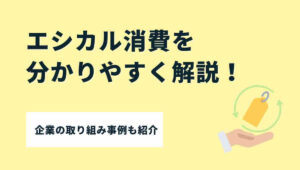環境問題に関心を寄せる人が増え、リサイクルやリユース、リメイクなどに加えて「アップサイクル」に関心をもつ人が増えてきました。
 お客様
お客様「アップサイクル」って聞きなれない言葉だけれど、今後どんどん増えていくのかしら?



そうですね。本来ゴミを削減できるアップサイクルは、環境に優しいものです。2025年の今でも日本だけではなく、海外でアップサイクルが行われている事例も多いです。
この記事では、アップサイクルの仕組みや問題点、リサイクルとの違い、そしてよいアップサイクルの事例を丁寧に紹介します。この記事を読むことで、私たち消費者がどのようにアップサイクルに関わっていけば良いかを知ることができます。
アップサイクルとは?リサイクルとの違い
アップサイクルとは、不要になったものにデザインなどを施し、新たに価値を生み出す考え方です。「廃棄物を減らして、資源を循環する」という考え方に基づいて行われています。そのため、アップサイクルされた製品は、元の製品よりも価値が上がるというのが、言葉の定義となります。
例えば、身近なもので言えば古着をポーチやぬいぐるみに作り替えることをアップサイクルといいます。廃材をそのまま使用して、家具などを作ることも、アップサイクルだと言えます。
「ごみを有効活用する」というとリサイクルを思い浮かべる人も多いでしょう。しかし、アップサイクルとリサイクルは異なります。リサイクルは一度廃棄物を分解し、作り替えることを指します。対して、アップサイクルは廃棄物を素材に戻さず、そのまま新しい価値を生み出す考え方です。
さらに、リサイクルは分解するときに熱を加えたり、溶解したりする必要があるケースが多いです。対して、アップサイクルは廃棄物を素材に戻さないので、加熱したり溶解したりする必要がありません。



古着でポーチやぬいぐるみを作るのは「リメイク」ではないの?



リメイクとアップサイクルは異なりますが、リメイクやリサイクルといっても、実際はアップサイクルされている例もあります。アップサイクルは元々の価値よりも高いものを生み出すのに対し、。リメイクでは必ず価値が上がるとは限りません。
なので、過去にリメイクやリサイクルと呼ばれていたとしても、価値の高い製品を生み出していれば、アップサイクルだといるでしょう。
【アップサイクルとリサイクルの違い】
| アップサイクル | リサイクル | |
| 目的 | 価値やデザイン性を向上させる | 一度分解して原材料として再利用する |
| プロセス | 加工して新たな製品に生まれ変わらせる | 分解して素材へ戻す |
| エネルギーの使用量 | 加熱が必要ない場合が多い | 分解するときに加熱が必要な場合が多い |
| 環境への効果 | 廃棄物(ゴミ)が減る創造性が高まる | 廃棄物(ゴミ)が減る |
合わせて読みたい記事:2025年に知りたいプラスチック削減の取り組み・日本、海外の具体事例
アップサイクルの問題点
アップサイクルは、不要になったものに熱を加えたり、溶解したりしないので、環境にやさしい廃棄物の活用方法です。
しかし、実際には「本当に環境問題解決の役に立っているのか?」といった意見があることも事実です。次の項目では、アップサイクルの問題点について詳しく解説します。
1.手間と価格が高い
アップサイクルは、リサイクルに比べると、加工に手間がかかり、新たな価値を加えるアイディアが必要になります。1つ1つの商品に、手間とアイディアが必要になる点は、アップサイクルの問題点のひとつだと言えるでしょう。
人手や予算がある大企業では、特に問題なくアップサイクルを行えるでしょう。対して、予算や人手が少ない中小企業や個人では、アップサイクルを継続的に行いづらい問題点があります。
また、元々のモノの価値よりも販売価格が高くなるため、購入しづらくなるという問題点もあります。本当に消費者が必要としているものを作成しないと、売れ残ってまた廃棄物となってしまう可能性もあります。
2.環境へ貢献度が少ない可能性がある
アップサイクルは、廃棄物となった製品の寿命を伸ばしたり、廃棄物を減らしたりすることに役立ちます。
しかし、実際に原材料や輸送、加工に関する温室効果ガスの排出を減らせるケースばかりではありません。環境に良いと言われているアップサイクルですが、実際にどのくらい環境にいいのか証明ができないのが実情です。
学校や自治体でもアップサイクルが行われている例があります。例えば、空き缶や牛乳パックなどでインテリア小物を作れば、廃棄物に新しい価値を与えるという教育にはなるでしょう。しかし、実用的で長く使えるものを作るレベルにまでは至らないのが現状です。
合わせて読みたい記事:グリーントランスフォーメーション(GX)事例|日本と海外の最新取り組みを紹介
3.大量の廃品処理には向かない
アップサイクルは、廃棄物をひとつひとつ処理しなければいけないので、大量に出る廃棄物を処理するのには向いていないと言えます。
とくに、個人や中小企業などの人手が限られているケースでは、廃棄物が処理できる量が限られています。大量の廃棄物をアップサイクルしたい場合、多くの時間と人手が必要になる点はアップサイクルの課題だと言えるでしょう。
合わせて読みたい記事:ネイチャーポジティブの国内・海外取り組み事例6選
4.グリーンウォッシュ
グリーンウォッシュとは、企業などで環境への貢献活動を行っているにも関わらず、結果的に宣伝やブランドイメージ向上のための取り組みで終わってしまう状態のことを言います。
グリーンウォッシュになってしまうと、見せかけの環境問題への取り組みが増えていきます。アップサイクルもグリーンウォッシュとなってしまうことがあり、消費者は「本当に環境に役立っているのか」を判断し、商品を購入しなければいけません。



グリーンウォッシュって具体的にいうとどんなこと?



例えば、衣料品ブランドが衣服の回収を行っていても、シーズンごとに衣服の大量に生産し、販売するのが環境に悪いという矛盾が起こってしまいます。見せかけの環境問題への対策では、実際に温室効果ガスの削減などの効果が出ません。



なるほど。確かに、環境にいい行動をしていても、それ以上のCO2を排出する事業をしていれば、結果的にマイナスになってしまうわね。



そうなんです。グリーンウォッシュについては、下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひ一度目を通してみてくださいね。
合わせて読みたい記事:グリーンウォッシュの実態とこれからー“サステナブル”の裏に潜む罠を知る
アップサイクルは世の中に受け入れられているの?
日本や海外では、アップサイクルされた商品が多く販売されています。しかし、アップサイクルには「本当に環境への役に立っているのか?」が分かりにくいという問題点があり、アップサイクル製品の購入に迷っている人も多いです。
とくに、SNSをよく利用する10代から20代はエコに関する知識が多いものの、グリーンウォッシュなどの情報にも厳しい目を持っています。30代から50代は、アップサイクルに関して機能性と価格のバランスを重視する人が多い傾向です。
60代以上では、アップサイクルを活用したアップサイクルの商品を購入したり、高い興味を持っていたりする人が多いです。しかし、情報源が限られていて、新しい商品やサービスに抵抗がある人が多く、購入や行動に繋がらないケースも多いです。



年代によってアップサイクルへの興味や購入意欲は違うのね。確かに、私も「本当にエコなのかな?」と考えてしまうと、どの商品を選べばいいか分からなくなることがあるわ。



そうですよね。グリーンウォッシュなどがあると、本当に環境に優しい商品の見極めが難しいという問題も出てきます
今後、アップサイクルも含め、消費者が商品についてリサーチしなくても、本当に環境に良いものが選べるような仕組みができることが望まれます。
合わせて読みたい記事:ネイチャーポジティブの国内・海外取り組み事例6選
アップサイクルをルール化するフランスの取り組み
フランスでは、アップサイクルをルール化する「反廃棄・循環経済法」が2020年に制定されました。反廃棄・循環経済法は、不要になったものは、簡単にアップサイクルやリサイクルできるように設計し、廃棄物を極限まで少なくすることが制定されています。
スマートフォンやノートパソコン、テレビなどの電化製品は、修理のしやすさや部品の入手しやすさなどで0から10点の評価を付けられるのが特徴です。(修理可能指数)
電化製品を販売しているメーカーは、製品の販売終了後も一定期間修理のためのスペア部品の供給を義務付けています。購入する段階から、長く使用し続けられる製品を選ぶことができ、廃棄物も減らすことができる環境にも消費者にもやさしい法律だと言えるでしょう。
また、EU全体では「修理する権利」に関する法制化が進められています。いくらモノを長く使用したいと思っても、修理方法がわからなかったり、部品がなかったりすれば新しいものを買わざるをません。このような事態を避けるべく、2024年には、消費者が家電製品を長く使い続けられるよう、修理情報提供義務などが採択されています。
反廃棄・循環経済法と「修理する権利」に関する法制化は、修理しながら長く使える製品を販売する企業の価値が上がるような社会を作っていくでしょう。
合わせて読みたい記事:生成AIに伴う環境負荷とは?データセンター増加で電力を大量消費
アップサイクルを実現するために重要なこと
アップサイクルを実現するためには、アップサイクルされた製品の情報やCO2削減量を見える化し、長く使えるモノづくりを徹底することが大切です。アップサイクルは、ゴミを減らせる素晴らしい考え方ですが、アップサイクルだけでは大幅なCO2削減が難しいのが現状です。
また、企業イメージの向上のために使われているという側面もあり、より消費者に伝わりやすいように情報共有が必要になるでしょう。とくに、フランスのように任意ではなくアップサイクルを義務に変え、社会全体での基準を作ることが大切だと言えます。
トレーサビリティを明確にする
トレーサビリティとは、製品の原料調達から廃棄されるまでを見える化する状態のことを指します。トレーサビリティを可能にすることで、アップサイクルされた製品が環境の役に立っているのかを、消費者が知ることができます。
例えば、廃棄予定だった空き缶を使ってアップサイクルを行うとき、加工して販売しなければ意味がありません。また、製品をアップサイクルするとき、新しく購入した材料を大量に使用するなどの工程があっては本末転倒です。
このように、アップサイクルを実現するためには、ひとつひとつの製品が、本当の意味で環境のためになっているのかを見える化する必要があります。
合わせて読みたい記事:脱炭素社会とは? 簡単・分かりやすい用語解説|地球環境をどう守る?
定量評価を取り入れる
トレーサビリティと同様に、アップサイクル製品のCO2削減量を見える化することも大切です。
どの製品がより環境に負担がないのか、どの製品が長く使い続けられるかを知っておくことで、消費者がよりいい選択ができるようになるでしょう。
レンタルや長く使えるモノづくりの検討をする
アップサイクルと共に取り組まなければいけないのが、製品のレンタルや長く使える製品づくりへの取り組みです。いくらアップサイクルが盛んに行われても、すぐ壊れてしまう製品ばかりでは廃棄物は減りません。
廃棄するモノを減らし、資源を循環させるためには、ひとつのモノをより長く使用する必要があります。長く使用できるものを選んで購入したり、レンタルなどを利用したりすることで、廃棄物を減らすことにも役立つでしょう。
減った廃棄物をもっと減らすためにアップサイクルを行うことで、廃棄物がほとんど出ない社会を目指すことも可能になるでしょう。
合わせて読みたい記事:SDGsと脱炭素は関係あるの?それぞれの意味や役割を紹介
アップサイクルの有益な取り組み事例
アップサイクルは、個人が取り組むよりも企業や自治体が取り組んだ方が、高い効果を得られます。個人の方は、アップサイクルされた商品やレンタルの利用、循環型商品を選ぶことで、環境へ貢献することが可能です。
企業や政府だけではなく、個人の一人一人が日々の選択を変えていくことで、環境にやさしい資源の循環を目指せるでしょう。
CLAS(クラス)|家具・家電のサブスクレンタル
CLASは、家電や家具などをレンタルできるサービスです。洗濯機やフィットネスバイク、ベッド、布団、電子レンジなど、幅広い商品をレンタル可能です。
レンタルした商品は後から購入もでき「まずは試しに使ってみたい」という製品をレンタルする使い方もおすすめです。契約期間の縛りもないので、使わなかったり、不要だったりした場合はすぐに返却できます。
CLASのようなレンタルサービスを利用することで、製品を長く使用して、廃棄物を減らせるメリットがあります。アップサイクルについて興味がある方は、ぜひCLASのようなレンタルサービスを利用してみてくださいね。
公式サイト:https://clas.style
airCloset:洋服レンタルでシェア型消費
エアクローゼットは、プロがコーディネートした洋服が毎月届くサービスです。洋服を長く着たいと思っても、長持ちさせるための手間をかけられないという人も多いのではないでしょうか。
とくに、洋服は大量に生産・消費されており、リサイクル率も低いのが現状です。そこで、エアークローゼットなどの洋服レンタルサービスを利用すれば、廃棄物を減らしながらおしゃれを楽しめます。
今まで洋服の廃棄に疑問を持っていた方に加え、プロが選んだコーディネートを楽しみたい方は、ぜひ利用を検討してみましょう。
公式サイト:https://www.air-closet.com/
TerrUP:アップサイクルした家具を販売
京都発の家具ブランドであるTerrUPは、アップサイクルで作られた家具を販売しています。TerrUPのアップサイクル商品に使われているのは、普段私たちが使っている使い捨ての竹箸です。
TerrUPのアップサイクル家具は、机やインテリア用品になって販売されています。おしゃれな家具ブランドの手によって、竹箸だとは分からないほどスタイリッシュな商品が販売されています。
ブランドや企業が作ったアップサイクル商品を購入することは、環境保護活動の一環となります。とくに、TerrUPの家具はスタイリッシュでおしゃれな製品ばかりなので、気になる方はぜひ購入を検討してみてくださいね。
公式サイト:https://store.nestrobe.com
まとめ:より意味のあるアップサイクルを実現するには
アップサイクルについて、あなたはどう感じましたか?一言でアップサイクルと言っても、本当に環境に優しいかどうかは商品について調べてみなければ分かりません。
アップサイクル製品を購入するときは、イメージ戦略としてアップサイクルを行っている会社ではなく、長く使えて、実際に環境に貢献している企業や商品を選ぶ視点が大切です。
この記事では、アップサイクルの重要性に加え、問題点も詳しく解説しました。この記事の内容を参考に、あなたがアップサイクルとどう関わりたいかを考えてみてくださいね。
そして、アップサイクルのような「モノを選ぶ視点」だけでなく、「エネルギーの選び方」もまた、これからの環境を考えるうえで欠かせません。
私たち「地球未来図」では、“これからの環境問題”に向き合うための情報として、脱炭素・ネイチャーポジティブ、そして太陽光発電の知識をわかりやすく紹介しています。
太陽光発電は、環境にやさしいだけでなく、電気代の削減や補助金の活用といった、家計にもメリットのある選択肢です。
「環境にいいこと、何か始めてみたい」 そんな方は、ぜひこちらの記事【ピタエネのひみつ】をのぞいてみてください。