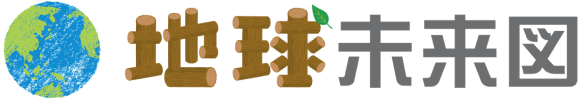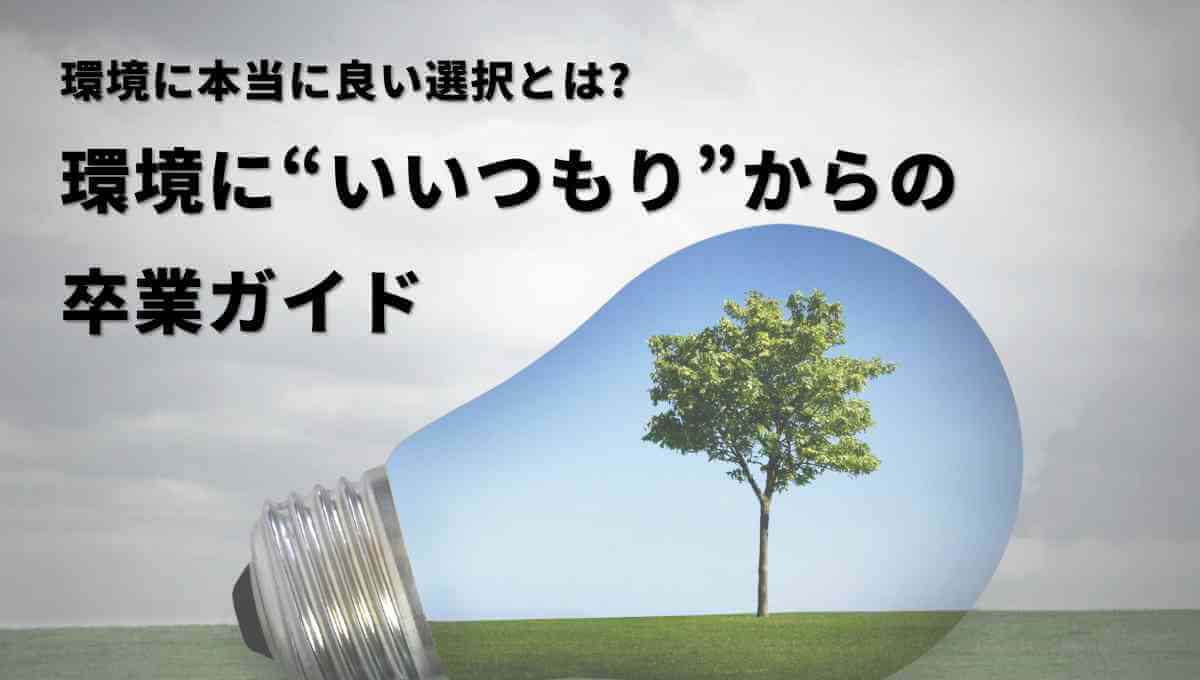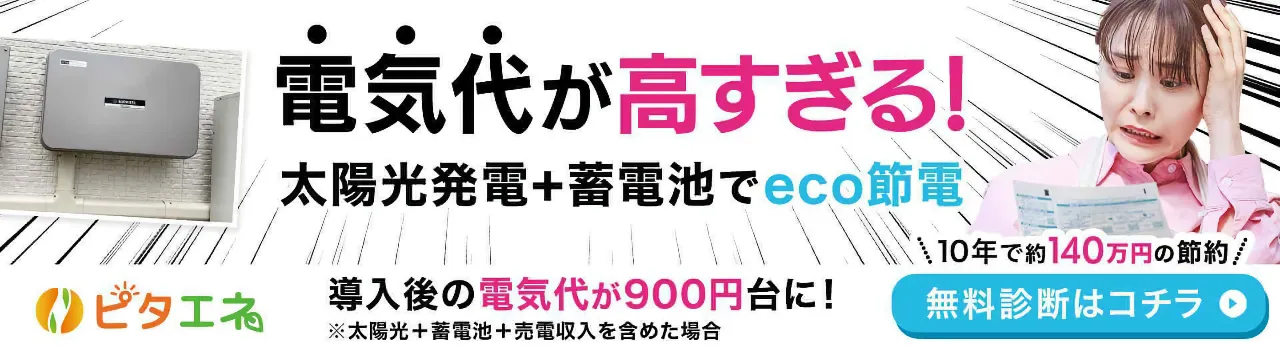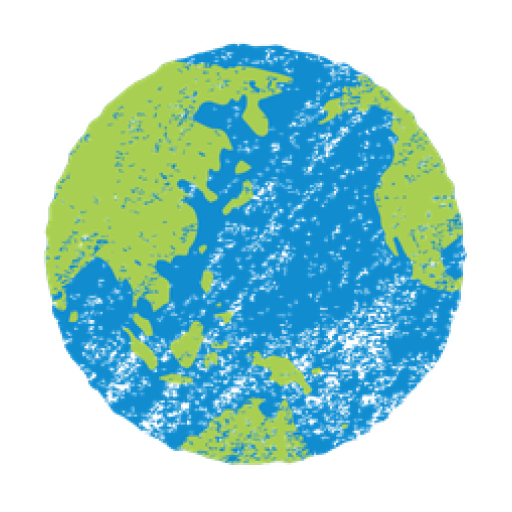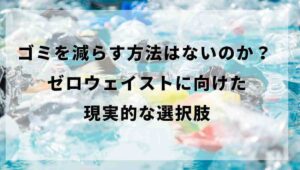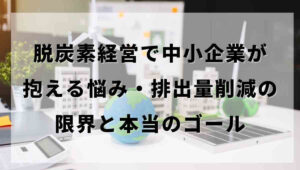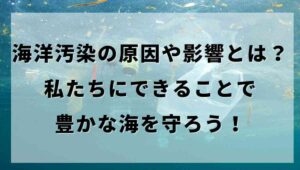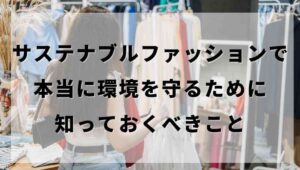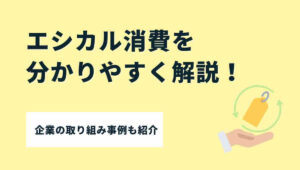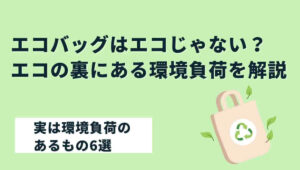「環境にいいはず」と思って選んだ製品やサービスが、実はそれほど意味を持たない―そんな“つもりエコ”が、私たちの身の回りには少なくありません。
パッと見は良さそうでも、実態は排出量や資源の無駄遣いがむしろ増えてしまうケースもあります。
2025年現在、こうした曖昧な「環境へのやさしさ」に対し、欧米を中心に日本でもユーザーの目はどんどん厳しくなっています。そして見せかけの広告(グリーンウォッシュ)対策や環境への貢献度を数字で分かるようにする“見える化”が本格化してきています。
「地球未来図」ではこれまで、脱炭素、再エネ、GX、循環経済、ネイチャーポジティブなど、
国内外の多彩な取り組みを中立的な視点で紹介してきました。
本記事は、そのシリーズの総まとめとして私たちの日常に潜む“つもりエコ”の仕組みと、
これから本当に環境に良い選択をするために必要な視点を一つに整理したガイドとなっています。
ファッション、小売り、AIの電力消費など、身近なテーマを手がかりに、“良さそうに見えるエコ”から卒業し、これからの時代にふさわしい環境との向き合い方を紹介します。
詳しい事例やデータは関連記事でも取り上げていますので、あわせてご覧ください。
見せかけのエコとはどんなもの?
環境に良さそうに見える商品・サービズ・取り組みでも、実際には効果がほとんどなかったり、根拠があいまいなまま広まっているものがあります。こうした“見せかけのエコ”の代表的な例のひとつが「グリーンウォッシュ」と呼ばれるケースです。
グリーンウォッシュは企業や商品が、実態以上に環境に配慮しているように見せることを指します。たとえば、具体的な根拠を示さずに「エコ」「自然に優しい」といった言葉を商品パッケージ、広告、販売説明で使われているケースがあります。
また、プラスチック梱包から紙の梱包に変更することで、プラスチック利用の削減に貢献をしていても、逆に輸送にかかるガソリンの量や時間、梱包に使われる資源などが増えているケースなど、一部の改善だけを取り上げて全体がすべて改善したように見せかける行為も含まれます。
情報が多い時代だからこそ、表面的な印象だけで判断してしまうと、本当に効果のある取り組みを見逃してしまう可能性があります。
グリーンウォッシュの身近な事例や海外で起きた大企業の裁判例、見分ける方法などは、以下の記事の中でさらに詳しく紹介しています。
合わせて読みたい記事:グリーンウォッシュの実態とこれからー“サステナブル”の裏に潜む罠を知る
ファッション・小売りの環境問題
日用品や衣料品の買い物という日常生活の中では、『環境にやさしい』商品をよく見かけますが、一方で、ファッションや小売りの世界では「つもりエコ」が生まれやすい状況があります。
商品のパッケージやお店のウェブサイトをパッと見ただけででは、その企業やサービスの環境への取り組みを理解することは簡単ではありません。
素材づくりや輸送、使用後の処分など、実はさまざまな場面で環境負荷が隠れていることがよくあります。
ここでは代表的な3つの例を取り上げてみます。
エコバッグは本当にエコか
 地球未来図
地球未来図綿素材のエコバックをプラスチックのレジ袋の変わりにすると、最低でも7,100回使用しなければレジ袋よりも環境負荷が上回ってしまう
このような研究結果があるのをご存じでしょうか?
綿の素材を作るには、製造過程で、大量の水・農薬、さらにエネルギーが必要になります。プラスチックやナイロン素材に比べて、重たい綿素材のバッグは梱包や輸送の際にもより多くの資材やエネルギーが必要になります。



じゃあ、プラスチックのバッグを使い続ける方がいいのかしら?



難しい質問です
ビニール製のレジ袋の問題点は、
1.大量に使い捨てが発生すること
2.ポイ捨てされた場合に、自然に還らず、鳥・動物・海洋生物に害を与えること
の2つがあげられます。しかし、綿素材のエコバッグには「自然還元」されるという意味では、環境に負荷のない素材です。
布製のエコバッグを7000回(20年)使うとうのは、実際には現実的ではありません。私たちにできる現実的な方法としては、エコバッグの素材に関わらず、なるべく長く強く使用できるものを選ぶことです。また”環境のため”といいながら、エコバッグと大量配布する行為などは、2025年現在、「本当に環境のためになっている」とは言い切れないことを知っておきましょう。
「エコバッグの環境負荷」に関するさらに詳しい情報や、環境にいいと勘違いされているものの事例は、以下の記事でもまとめていますので是非ご覧ください。
合わせて読みたい記事:エコバッグはエコじゃない?実は環境負荷のあるもの6選
アップサイクルの可能性と限界
アップサイクルとは、不要になったものにデザインや加工を施し、元より価値の高い製品として生まれ変わらせる取り組みです。古着をバッグや小物にしたり、廃材で家具やインテリアを作るなどの取り組みがよく知られています。
分解して素材に戻すリサイクルと違い、加熱や溶解を行わないため資源やエネルギーの利用をおさえられることで注目が集まっています。
ただし、手作業の負担が大きいため、大量の不用品の処理には向かず、また価格が高くなりやすい課題があります。不用品に新しい価値を与えるためにより多くの材料やエネルギーを利用してしまうと、結果的にグリーンウォッシュにつながるケースもあります。



無理のない範囲で、廃材活用を行っていくのがよさそうね



モノを捨てるのではなく、修理することは重要です。フランスでは「修理を義務化」する制度も作られ始めており、買う前から、どのように「モノ」と付き合っていくのかを考える姿勢が求められるようになっています。
アップサイクルやサステナブルな買い物、ファッションに関する詳しい事例や、今後の課題は以下の記事にまとめています。
合わせて読みたい記事:アップサイクルの現状・事例から問題点と可能性を考える
合わせて読みたい記事:サステナブルファッションで本当に環境を守るために知っておくべきこと
生成AIの普及に伴うエネルギー負荷
近年急速に一般化し、利用者の増えているのが生成AIですが、その裏側に大規模な電力消費があることはあまり知られていません。
生成AIを動かすために必要な”データセンター”には、膨大なデータを処理する高性能チップを搭載したサーバーが集まり、24時間稼働を続けています。とくに画像や動画を扱う生成AIは特に電力消費が大きく、一般的なデータ処理の数倍~100倍近い電力が必要になるとされています。
国際エネルギー機関(IEA)はAI関連データセンターの需要が2030年までに年15%増加すると予測しています。そして、ひとつのデータセンターでは一般家庭1万〜1万6千世帯分の電気が必要になる例もあると報告されています。
さらに、データセンターには冷却用の水も必要になります。アメリカバージニア州では2019〜2023年で水消費量が63%増え、少なくとも70億リットルがデータセンターに使用されたと報告されています。



AIを使うことでむしろ電気の利用は効率的に減らせるのだと思っていたわ



AI の電力消費を劇的に下げる技術は既に研究されているため、必要な電力も今後減っていく期待ができます。
一方でAIの利用がそれを上回って急速に増えているため、どのように環境とAIの電力消費のバランスをとるのかは、これからの課題となっています。
合わせて読みたい記事:生成AIに伴う環境負荷とは?データセンター増加で電力を大量消費
これから何が起こるのか
2026年以降、環境分野では「見える化」がより強く求められるようになります。これまで曖昧だった環境効果をイメージではなく、数値で示すことが国際的な基準になり、企業も生活者も“実際に効果のある取り組みかどうか”で判断する時代に入っていくでしょう。



これまでよりも分かりやすくなるのね。安心したわ
GX(グリーントランスフォーメーション)による「見える化」の加速
GXは、エネルギー転換や産業構造の改革を通じて、経済成長と環境配慮を両立させる動きです。GX化と並行し、各国で排出量の公開が義務化されつつあり、日本でも企業活動の透明性が重要になっています。この流れが強まるほど、見せかけのエコは成立しにくくなり、本質的な取り組みが評価されるようになっていくでしょう。
合わせて読みたい記事:グリーントランスフォーメーション(GX)事例|日本と海外の最新取り組みを紹介
脱炭素と再生可能エネルギーが最重要テーマに
2025年に脱炭素がこれまで以上に注目されているのは、気候変動が“もう待てない段階”に入っているからです。近年の猛暑や豪雨、森林火災の増加からも、温暖化への危機感は一段階上のレベルに上がっています。国連の専門機関は「2030年までに世界のCO₂排出を大きく減らさないと、気温上昇を1.5℃以内におさえるのが難しくなる」と警告しており、2025年はその目標まであと5年という重要な節目です。
世界中が「今すぐ行動しなければ間に合わない」と考え始めているのです。
このため、世界のさまざまなルールが急速に脱炭素ありきに切り替わっています。EUでは、CO₂の排出が多い製品には追加コストがかかる仕組みが始まり、企業には排出量の開示を求める動きも広がっています。「環境に良いと望ましい」ではなく、「対応しなければビジネスで不利になる」という時代に変わり、日本企業も例外ではありません。また、脱炭素は環境だけの問題ではなく、世界の経済競争の中心にもなっています。アメリカやEU、中国は再エネ、蓄電池、EVなどの分野に巨額の投資を進め、新しい産業を育てようとしています。
私たちの日常生活の中でも、電気代の高騰にそなえ、国内での安定した電気の自給自足を行うためにも、太陽光や風力などの再生可能エネルギーは、家庭や地域を守る“現実的な選択肢”となっています。
このような背景から「環境にやさしい選択」のなかでも、脱炭素は環境・経済・暮らしを同時に支える最重要テーマとして位置づけられています。
合わせて読みたい記事:脱炭素社会とは? 簡単・分かりやすい用語解説|地球環境をどう守る?
合わせて読みたい記事:【最新】日本の発電方法ランキング・再生可能エネルギーの普及はどれくらい?
合わせて読みたい記事:カーボンニュートラルの具体例13選|国内・海外の最新事例を紹介
サーキュラーエコノミー・持続と循環
サーキュラーエコノミー(循環経済)は、資源を「使い捨て」から「循環」へ移行させる考え方です。これまでの“環境に良さそう”なものを選ぶ段階から、資源の流れそのものを見直す段階に入っています。再利用、再資源化、修理、共有などが評価対象となり、企業も生活者も“循環を前提とした選択”が重要になっていくでしょう。
サスティナビリティ(持続可能性)がこれまではよく取り上げられてきましたが、それと並行した考え方としてさらに注目を集めていくでしょう。
合わせて読みたい記事:サーキュラーエコノミーとは?循環型社会を実現する仕組み
まとめ
ここまで紹介したように環境への取り組みは以前までとは違って、非常に複雑になり、どのような活動やサービス・商品が環境への貢献度が高いのかの判断はより難しくなっています。近年の気候変動やAIなど新しい技術の影響により、将来の予測不可能な状態が、この先も続いていくことでしょう。
そんな中、環境に関わるニュースや新しい取り組みを取り入れておくことが重要です。
「地球未来図」では、こうした“これからの環境問題”に向き合うための情報として、脱炭素、ネイチャーポジティブ、再エネ、GXなどの最新テーマをわかりやすく紹介しています。中でも太陽光発電は、環境への貢献だけでなく、電気代の削減や補助金の活用など、日々の暮らしに直接メリットのある選択肢のひとつです。
「環境にいいこと、なにか始めてみたい」「自宅でもできる取り組みを知りたい」そんな方には、太陽光の基礎知識や導入のポイントを丁寧にまとめた『ピタエネのひみつ』もご用意しています。初めての方でも安心して検討できる内容になっていますので、ぜひ参考にしてみてください。
「環境にいいこと、何か始めてみたい」そんな方は、ぜひ「ピタエネのひみつ」をご覧ください。
合わせて読みたい記事:海洋汚染の原因や影響とは?私たちにできることで豊かな海を守ろう!
合わせて読みたい記事:2025年に知りたいプラスチック削減の取り組み・日本、海外の具体事例