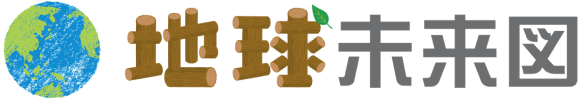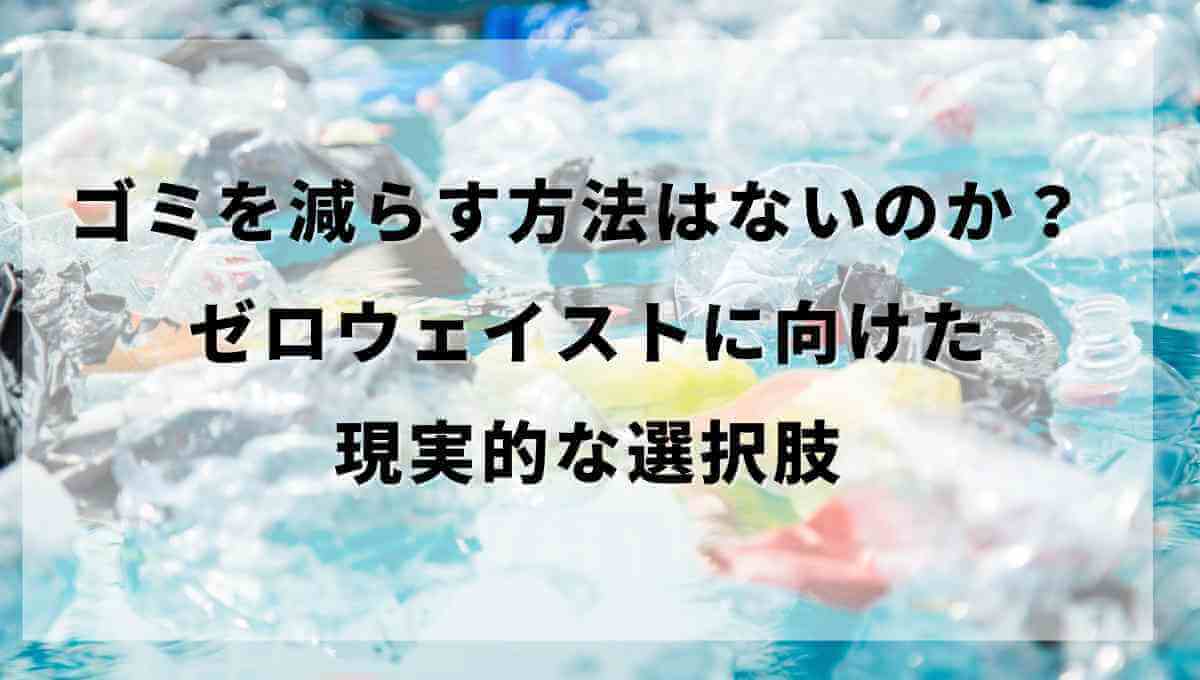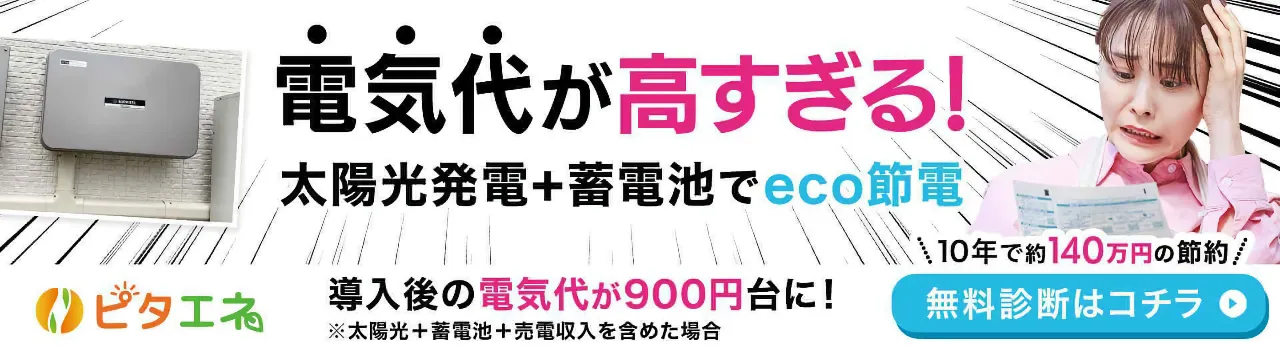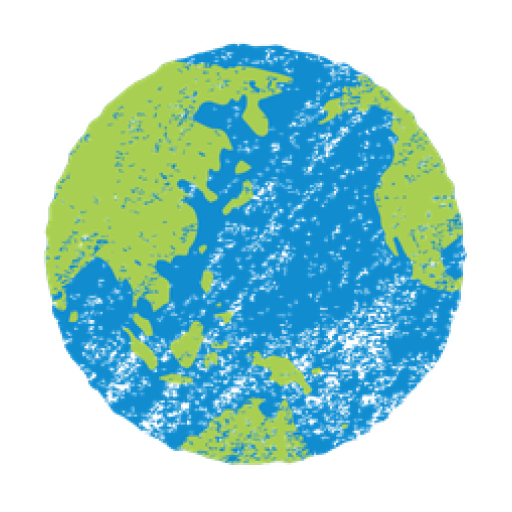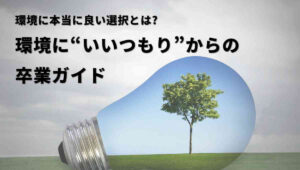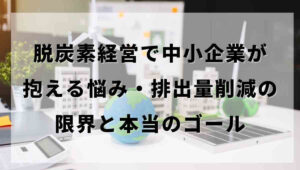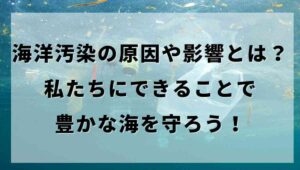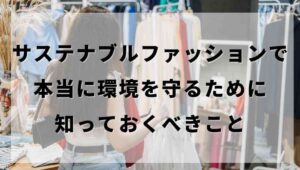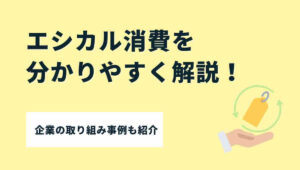環境への影響を考えると、少しでもゴミを減らしていきたいと思って行動している方は多いです。しかし、ゴミを減らそうと思っても、実際に行動に移すのは難しいと感じている人も多いのではないでしょうか。
現代はゴミが多く出ており、ゴミを燃やすことによる環境への影響や、マイクロプラスチックによる野生生物への影響などが懸念されています。2023年度の産業ゴミと家庭ゴミを合わせると、日本人が1日あたりに出しているゴミは、一人あたり851gにも及びます。(参照1)
国民一人あたり1日に1キロ近くのゴミを出していることに驚く人も多いのではないでしょうか。この記事では、ゴミを減らすためにできることに加え、ゴミを減らして環境に貢献するための本質について解説します。
 お客様
お客様ゴミを減らすように頑張っているけれど、個人でいくらゴミを減らしても環境に貢献できているのか分からないわ。



この記事はゴミを減らして、環境に貢献したいと考えている人に読んでほしい記事です。記事内では、実際に今からできるゴミ問題への事例を紹介します。「ゴミを減らしたい」と感じている方は、ぜひ最後まで目を通してみてくださいね。
1.なぜゴミが多いとよくないのか
ゴミを減らす対策として、買い物時のレジ袋の有料化や資源のリサイクルなどが行われています。個人だけではなく、政府が法改正などをしてゴミを減らそうとしている理由には、下記のようなものがあります。
- ゴミを燃やして処理することでCO2などの大気汚染物質が出る
- 海や土壌がマイクロプラスチックで汚染される(プラスチックの分解には数百年かかる)
- マイクロプラスチックの影響で生態系の破壊につながる
- ゴミとなる容器や製品を作るときに大量の資源とエネルギーを使用する
ゴミが多いと良くないとされる理由の大部分には、ゴミを処理するときの大気汚染にあります。ゴミを燃やして処理することで、地球温暖化の原因となるCO2などが多く排出され環境汚染につながるのです。
さらに、私たちがよく使用するプラスチック製品は、分解に数百年の時間がかかります。正しく処理されなかったプラスチックは、海などでマイクロプラスチック化し、動物たちの生態系に悪影響を及ぼしています。ポイ捨てされたプラスチックゴミを野生動物が食べてしまったり、絡まったりすることが問題となるケースもあります。
合わせて読みたい記事:2025年に知りたいプラスチック削減の取り組み・日本、海外の具体事例
2.ゴミ問題に日本はどう取り組んできた?
ゴミ問題は、利便性が高まった2000年代から始まりました。次の項目で、1970年代より前の時代から順を追ってゴミ問題についてみていきましょう。ゴミ問題の歴史や取り組みを知ることで、ゴミ問題に対する考えが深められますよ。
1970年代以前
ゴミ問題は2000年代からより問題視されるようになりました。100年以上前の1970年代の日本では、ほとんどの日用品が木や鉄、陶器、ガラスなどの再利用できる素材で作られていました。プラスチックの利用は現代に比べると極端に少なく、今に比べるとゴミも極端に少なかったのです。
例えば、使ったらゴミとなってしまう紙おむつは、1970年代前半から日本で発売され始めました。1970年以前には、紙おむつはまだ日本になく、布オムツを再利用していたのです。高度成長期である1970年代から様々な便利なものが登場し、経済の発展につれゴミの量が増えていきます。
1970年-2000年代
日本のゴミ問題のピークは2000年代です。以下の表を見ると、1970年からゴミが増えていき、1997年から減っているのがわかります。1990年代から2000年代は1人1日あたりのゴミの排出量は約1,100〜1,200gでした。対して、2023年度は851gまで減っています。(参照1)
2000年代から現代にかけてゴミが減っている理由は、増えすぎたゴミを「問題」と認識し、ゴミを減らすための取り組みが行われ始めたためです。1990年代では、ゴミの処理方法に関する議論が活発にされていました。対して、2025年である今は、リサイクルやリユースなどの活動で「いかにゴミを出さないか」を中心に議論が行われています。
年代によって、ゴミ問題に対処する方法が変わってきているのです。
| 年代 | 一年あたりのゴミの排出量 |
| 1970年 | 2810万トン(参照2) |
| 1980年 | 4394万トン(参照2) |
| 1997年 | 5120万トン(参照3) |
| 2010年 | 4,536万トン(参照4) |
| 2020年 | 4,167万 トン(参照5) |
| 2023年 | 3,897万トン(参照1) |
参照1:https://www.env.go.jp/press/press_04470.html
参照2:https://www.env.go.jp/recycle/circul/venous_industry/ja/history.pdf
参照3:https://www.env.go.jp/recycle/kosei_press/h000623a/h000623a-1.html
参照4:https://www.env.go.jp/press/15007.html
参照5:https://www.env.go.jp/press/110813.html
合わせて読みたい記事:ネイチャーポジティブの国内・海外取り組み事例6選
現代(2010〜2025年)
2025年の現代では、2000年代に比べるとゴミの排出量は減っています。ただ、プラスチックを使用した使い捨て容器や包装のゴミは増えています。商品を売る企業も、商品を購入する消費者も、便利で衛生的かつ低価格な商品を販売(購入)したいという傾向が強いためです。
日本の家庭ゴミのうち、プラスチックゴミは重量で約2割から3割、堆積では約6割を占めます。最近では、どんな商品もプラスチックからできたパッケージや容器に入っており、商品を買えばゴミとなるプラスチックパッケージや容器がついてきます。
また、スマホやパソコン、家電なども短い期間で新製品が出て頻繁に廃棄されています。電化製品を長く使いたいと思っても、修理の方が高くなってしまったり、そもそも部品が製造中止にいなっていたりして、長く使いたくても使えないというケースも多いです。
今後、日本のゴミを減らしていくためには、プラスチックパッケージの利用を控えたり、長く使用できる商品作りが必要不可欠です。
合わせて読みたい記事:サステナブルファッションで本当に環境を守るために、知っておくべきこと
3.現代生活でゴミをなくすことの難しさと取り組み
ゴミを減らそうとしている方の中には、日常生活でゴミを出さないことが難しいと体感した方も多いのではないでしょうか。ゴミをそもそも出さないようにすることは「ゼロウェイスト」とも呼ばれており、現代ではゼロウェイストの考え方にのっとり、ゴミを減らす活動を行っている方が多くいます。
ゼロウェイストは、大量生産と大量消費による環境への影響を抑えるために生まれました。ゼロウェイストに関する取り組みは、ゴミそのものを減らすだけではありません。ゴミを資源として扱いリサイクルを通して「循環型社会」を作り出すことが目的です。
便利さとゼロウェイストを両立するためには、生産者や販売する企業、消費者がそれぞれ考え方を変えていかなければいけません。ゴミ問題解決への難しさと解決法を知っておくことで、ゴミを減らしたい今どのように行動すればいいか分かります。
スーパーマーケット
日本では、1日あたり家庭ゴミだけで一人475gのゴミを出しています。(参照1)475gのうち、重量で2〜3割のゴミが容器や包装などで使用されたプラスチックゴミです。重さに換算すると、約95g〜140gのゴミがレジ袋やトレー、商品を包んでいるフィルムなどのパッケージから排出されています。
さらに、1日1人あたり約104gのフードロスも出ていることもご存じでしょうか。パッケージによるゴミを減らすことに加え、食べ残しや賞味買いすぎなどによるフードロスも削減することでゼロウェイスト実現に一歩近づきます。
ゼロウェイストを実現するためには、スーパーマーケットではなく青果店や精肉店、鮮魚店などの直売店で商品を購入するのが理想です。日用品は量り売りをしている店舗を利用することで、パッケージによるゴミの増加を抑えられるでしょう。
ただ、お肉や野菜、日用品などをそれぞれ異なる店で購入するのは難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。商品を異なる店で購入することで、移動のために時間もお金もかかるでしょう。さらに、地域によっては直売店や量り売りのお店が近くにないケースも多いです。
いきなりゴミをゼロにするのではなく、自分ができることから始めることが大切です。近くの量り売りの商品を利用したり、フードロス削減を意識したり、直売店を利用したりなど、できる範囲で選択を変えていきましょう。



直産市場や地域マルシェの活用もおすすめです。直産市場や地域マルシェは、生産者が消費者に直接商品を売ることができる市場のことです。消費者は新鮮な地元野菜を購入でき、生産者は規格外の商品も販売することで、パッケージゴミやフードロスも削減できます。



読者 ゴミを減らすこともできて、地域の生産者の応援もできるのね。近くで直産市場と地域マルシェがやってないか調べてみるわ!
合わせて読みたい記事:エシカル消費とは?メリットや私たちにできることをわかりやすく解説
外食・デリバリーフード
「自炊の方がエコ」だと思われがちですが、外食の方がゴミを減らせるケースがあります。飲食店では、一般家庭に比べると簡略化されたパッケージの商品を使用していることが多いです。また、飲食店やデリバリーでは、一括で調理を行うため使用するエネルギーが少ないメリットもあります。
さらに、近年は飲食店やデリバリーの利用で出るゴミを減らすため、食器を回収する「megloo(メグルー)」というサービスも登場しています。メグルーでは、テイクアウトで利用した容器を回収し、洗浄して再利用することで、テイクアウト時のゴミを減らせるサービスです。このようなサービスを実施している店舗を活用することで、外食でもゴミを減らす選択が可能です。
ただし、容器回収サービスは、テイクアウトを利用した人が回収に協力しないと意味がありません。ゴミを減らすための取り組みに協力するときは、容器の回収に協力するなどの消費者の協力が必要不可欠です。
外食やデリバリーでゴミを減らすためには、食器回収サービスを利用する、使い捨ての箸やスプーンは貰わないなどの選択が必要です。ゴミを減らす取り組みを行っている企業の商品を購入することも、ゼロウェイスト実現に貢献する選択となります。
合わせて読みたい記事:エシカル消費とは?メリットや私たちにできることをわかりやすく解説
オンラインショッピング・宅配
オンラインショッピングや宅配では、スーパーマーケットなどの小売店に比べると、簡易包装などでゴミを減らしやすいです。ただし、過剰包装の宅配を選んでしまうと、逆にゴミが増えてしまうので注意しましょう。
また、便利だからといって、何度も分けて配送を頼んだり、頻繁に宅配を利用したりしていると、段ボールや包装などのゴミが増えてしまいます。オンラインショッピングや宅配などを使用するときは、まとめて配送や簡易包装を選択しましょう。



最近はオンラインショッピングでも「簡易包装」や「まとめて配送」を選択できるようになったわよね。



そうですね。近年は、環境への取り組みをしている企業も多く、様々な取り組みが行われています。
例えば、生協ではプラスチックの使用量を減らすために包装紙を小さくするなどの取り組みを行っています。また、カタログやチラシ、包装紙を回収してリサイクルすることで、ゴミを減らし循環型社会に貢献する取り組みも行っています。
このような取り組みを行っている企業の商品を購入して応援することも、ゴミを減らすための選択だと言えるでしょう。



そうだったのね!ゴミを減らす取り組みをしている企業の商品を購入すれば、企業も応援できてゴミも減らせて一石二鳥よね。
それでも私たちができること
現代において、ゴミを減らすのには限界があると感じる人も多いです。ゴミを減らすために詰め替え商品やリユースサービスを利用する場合も、時間だけではなくお金も多く必要になります。そもそも、近くに直売店や量り売りのお店がないというケースもあるでしょう。
ゼロウェイストを実現するためには、個人の選択に頼る方法だけではなく、国が制度を変えていく必要があります。「レジ袋有料化」のように、包装の簡略化や再利用などの仕組みづくり、法改正をしていかなければ根本的な解決は難しいです。
ただ、私たちが選択を変えることでゴミを減らし環境へ配慮した生活ができることも確かです。消費者が変わることで、企業もゴミとなる使い捨て容器や包装を減らす方向に向かいます。
日本では、サービスの一環で過剰包装や使い捨てのスプーンや箸をつけることもあります。お客さんのためを思ったサービスが、日本のゴミを増やす要因の一つになっているのです。
使い捨ての容器や箸、スプーンを使わず、量り売りなどのサービスの利用、ゼロウェイストをしている企業の支援など、私たちのひとつひとつの選択がゴミを減らすことにつながります。ゴミを減らせる商品やサービスを利用することで、企業が需要を感じとり好循環を生み出すことができます。
合わせて読みたい記事:海洋汚染の原因や影響とは?私たちにできることで豊かな海を守ろう!
まとめ:ゴミを本当に減らすための道のり
ゴミを減らすためには、ゴミを出さない仕組み作りが必要です。消費者の私たちにできるのは、ゴミとなるものを受け取らない姿勢を示すこと。日常のあらゆる場面で、ゴミを減らす選択が必要です。
近年は、アンケート調査でも環境に配慮したいと答える人が増えています。しかし、どうしても利便性や価格を取らなければいけない場面では「したくてもできない」という場面も出てくるでしょう。
日本政府もリサイクルに関する法整備を行っていますが、ゴミそのものを減らす仕組みはまだできていません。商品や買い物の利便性に加え、リサイクルしやすさなどの社会の仕組みを変えていくためにも、消費者である私たちがゴミを減らすという強い意志を持たなければいけないのです。
私たち「地球未来図」では、脱炭素社会や再生可能エネルギーに関する知識をわかりやすく伝えるだけでなく、実際に行動に移すための選択肢も紹介しています。
運営元のレオフォースは、太陽光発電を生活に取り入れる人を増やすために、ピタエネという太陽光発電設置の相談や代理店サービスも展開しています。
「環境のために、まず何か始めたい」そんな方は、ぜひこちらの特集【ピタエネのひみつ】もご覧ください。
※本記事は「ピタエネ」を紹介するPRコンテンツを含みます。