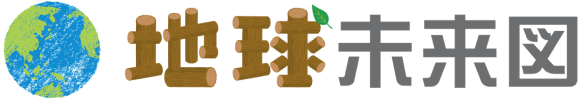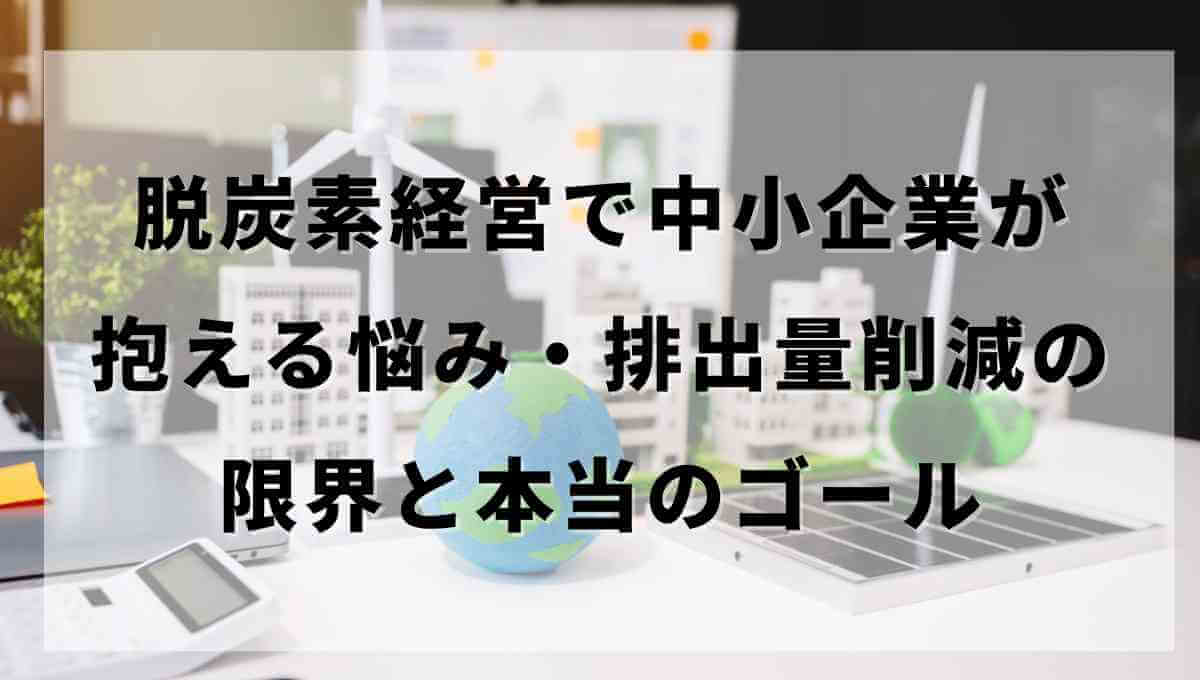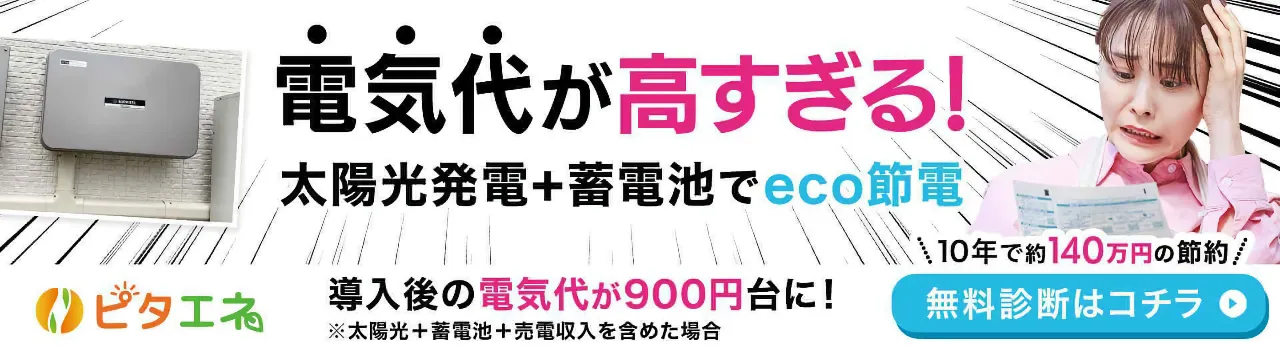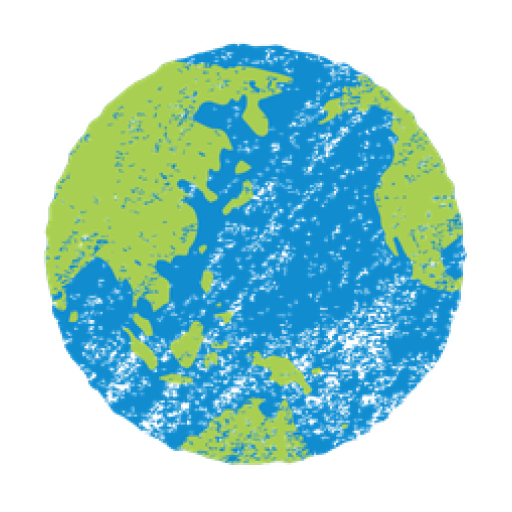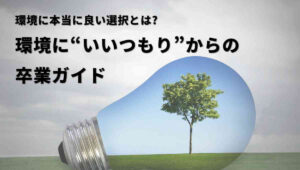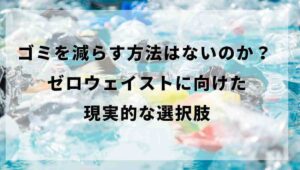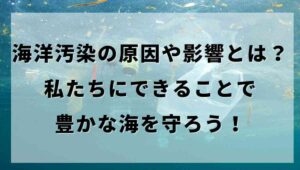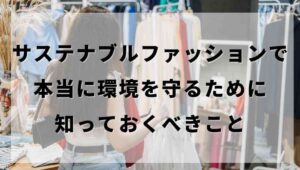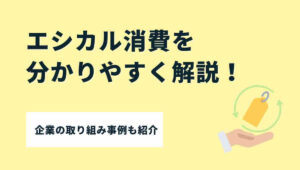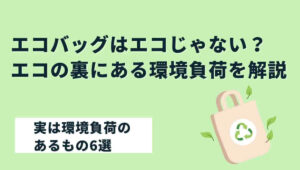脱炭素経営はもはや一部の大企業だけの課題ではなく、中規模・小規模の企業でも無視できない状況になっています。日本政府も2050年カーボンニュートラルやGX推進法を打ち出し、企業に対応を求めていいます。
しかし、脱炭素経営と聞いて自社に何ができるのか、どのように始めればよいか悩んでいる企業も多いでしょう。
この記事では、脱炭素経営をこれから始める中小企業の担当者が抱える排出量削減の限界や、そもそもどこを目指せばいいのかという根本的な悩みにお答えします。
時代のプレッシャーに流されて始めるのではなく、2025年の今、企業にとっての本当のゴールを見つけるための長期的な視点とヒントを解説します。
脱炭素経営とはどういう経営か
脱炭素経営とは事業活動で排出される温室効果ガス(主にCO2)の排出量を削減し、実質ゼロにすることを目指す経営のことです。気候変動による環境問題に貢献できるだけでなく、企業価値を高めるための重要な戦略となっています。
脱炭素経営が企業にとって重要な取り組みとなった背景として、国際的な合意や国内の法整備が深く関わっています。
2015年に開催されたCOP21(国連気候変動枠組条約締約国会議)でパリ協定が採択されたことで、「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」という長期目標が掲げられました。
パリ協定にもとづいて、日本政府は2020年10月に「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指す」と宣言し、企業が脱炭素経営に取り組む必要性を明確にしています。(参照1)
また、カーボンニュートラルの実現に向けた法的な枠組みとして2023年にはGX推進法(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律)が成立しました。脱炭素化を進める企業への投資促進や排出量取引制度の導入など、企業が脱炭素経営に取り組みやすくしています。
近年、日本政府が脱炭素への取り組みを推進していることもあり、投資家や消費者も企業の環境問題への取り組みを重要視する傾向にあります。脱炭素への取り組みが不十分だと企業の評価が下がったり、投資家や消費者に選ばれなくなったりする可能性があるでしょう。
脱炭素経営は企業の規模に関わらず、企業が社会的な責任を果たしつつ競争力を強化するための不可欠な経営戦略となっています。
参照1:資源エネルギー庁
合わせて読みたい記事:脱炭素社会とは? 簡単・分かりやすい用語解説|地球環境をどう守る?
脱炭素経営のはじめ方を分かりやすく解説
脱炭素経営と聞くと大企業が行う壮大なプロジェクトのように感じられるかもしれません。しかし、中小企業でもCO2排出量の可視化など、身近なところから始めることができます。ここでは、脱炭素経営の始め方を3つのステップに分けて分かりやすく解説します。
①STEP1:CO₂排出量を「見える化」
脱炭素経営を始める第一歩は自社のCO2排出量を算定し、「見える化」することです。見える化する範囲(スコープ)は以下の3つに分かれます。
| 範囲 | 概要 |
|---|---|
| Scope1 | 自社で直接排出するCO2(工場で燃料を燃やしたり、社用車でガソリンを使ったりすることで発生する排出量など) |
| Scope2 | 他社から供給されたエネルギーの使用に伴う間接的な排出量(オフィスや工場で使用する電気や熱など) |
| Scope3 | 事業活動全体に関わるその他の間接的な排出量(原材料の調達や製品の輸送など) |
自社で排出するCO2だけでなく、原材料の調達や製品の輸送など自社の事業活動によって他社が排出するCO2も算定する必要があります。
 お客様
お客様CO2排出量は実際に計測して正確な数値を算出しないといけないの?



すべてのスコープで計測しようとすると難易度が高くなってしまうため、排出原単位を使って簡易的に計算できるようになっています



排出原単位?



活動量あたりのCO2排出量のことです。電気1kWhを使用した場合のCO2排出量や貨物の輸送量1トンキロあたりのCO2排出量などの数値が定められています。
その数値に実際のエネルギー使用量や輸送距離などを乗じることで簡易的なCO2排出量を算出できます
排出原単位は環境省ホームページの「排出原単位データベース」にまとめられています。企業は電気使用料やガソリンの使用量、購入した原材料のデータなどを管理することで、排出量単位を活用してCO2排出量を算出ができるようになります。
脱炭素経営を実施している大企業ではデータの管理や排出量の算定にSaaS型の管理システムを使用するのが主流です。SaaS型の管理システムはAIや自動化でCO2排出量の見える化を効率的に行えます。
しかし、導入に数百万〜数千万円単位のコストが発生することもあるため、中小企業では導入が難しい場合も多いでしょう。予算が足りない場合の対策として以下が挙げられます。
- 中小企業向けの簡易ツール(エクセル連携型)や無料枠のあるSaaSを利用する
- 国や自治体の補助金で導入費用を抑える
- 段階的に「外部コンサル+シンプルな算定ツール」から始める
手作業で行うよりも効率的にCO2排出量の見える化を進められるため、担当者の負担を大幅に軽減できます。
②STEP2:目標設定とロードマップ作成
CO2排出量の見える化が可能になったら、次に具体的な目標を設定し達成するためのロードマップを作成します。
日本では2050年までにカーボンニュートラルを目指していることやSBT(Science Based Targets)を考慮して目標を設定します。SBTとはパリ協定の目標にもとづいて企業が設定する温室効果ガス削減目標のことです。
自社業界に合わせて、「2030年までにCO₂排出量を〇〇%削減する」といった中期的な目標と、「2050年までにカーボンニュートラルを実現する」といった長期的な目標を設定しましょう。ロードマップには、各目標を達成するための具体的な施策やそれぞれの担当者、期限などを記載します。
施策を実施する順番や投資回収年数、補助金の活用プラン、社内教育プランなども同時に作成します。
③STEP3:実行
計画的に立てたロードマップにもとづいて、具体的な脱炭素への取り組みを実行に移します。たとえば、以下のような取り組みが挙げられます。
- オフィスや工場で使用する照明をLEDに交換する
- オフィスや工場に太陽光パネルを設置する
- 高効率な空調設備に更新する
- 業務で使用する車両をEV(電気自動車)に切り替える
- 電力会社を再生可能エネルギーを供給している会社に変更する
実行後は、定期的にCO2排出量を算定し計画通りに進んでいるかをチェックします。実行と検証のサイクルを回すことで、持続的な脱炭素経営を実現できます。
合わせて読みたい記事:サステナブルファイナンスの実情・“本当”に環境に優しい取り組みとは?
脱炭素経営の限界
脱炭素経営は企業が取り組むべき社会的な責任であり、新たな成長機会でもあります。しかし、投資家や政府の補助金ばかりに目が行きがちで、実際に長期でどれほど環境に貢献できるのか曖昧な場合も少なくありません。
そもそも経済活動や消費そのものが環境を破壊している現状でこれらの施策では限界があるという環境専門家の声もあり、さまざまなジレンマに直面することもあります。ここでは、脱炭素経営を長期的な視点で捉えるために、知っておくべき課題について解説します。
①中小企業では削減余地が小さいこともある
中小企業では事業活動全体から排出されるCO2の絶対量が少ないため、削減のための努力や投資が成果として見えにくいことがあります。すでにLEDや省エネ機器の導入、物流の効率化を実施している企業では以下のような代案があるものの削減余地が小さくなります。
- 再生可能エネルギーの調達(電力会社の切り替え、PPA契約)
- サプライヤーや顧客と協働してScope3の排出量を削減
- カーボンクレジットを購入してCO2排出量と相殺
- 製品・サービスの「使う段階」のCO2排出量を削減(省エネ家電を設計するなど)
大企業ほど大幅にCO2排出量を削減できない傾向にあるため、単に排出量を減らすことを目標にするだけでは投資対効果が見合わないと感じてしまうかもしれません。
脱炭素への取り組みはブランドイメージの向上や優秀な人材の獲得にもつながります。企業にとってもメリットがあることを知っておけば、脱炭素経営に取り組みやすくなるでしょう。
合わせて読みたい記事:カーボンプライシングの仕組みと課題をわかりやすく・脱炭素社会の鍵となる行動は?
②サプライチェーンの排出削減の難易度が高い
自社だけでなく原材料の調達から製品の廃棄までのサプライチェーン全体(Scope3)のCO₂排出量を削減することは、非常に難易度の高い取り組みになります。自社の直接的な管理下にない外部の企業と協力する必要があるからです。
たとえば、製造業であれば部品の製造を担うサプライヤーや、製品の輸送を請け負う物流会社の排出量も削減対象となります。しかし、これらの企業に脱炭素への協力を強要することは難しく、個々の企業の努力だけでは限界があります。
また、原料や商品をアジア諸国からの輸入でまかなっている企業が圧倒的に多いことも考慮しなくてはなりません。日本本社から海外支部へ「再生可能エネルギーを導入してほしい」と求めても、現地には太陽光や風力を導入する資金や制度的後押しが不足している場合もあります。
現在のビジネスの在り方を脱炭素経営に合わせていきなり理想通りに変更することは、目に見えている以上に困難で時間も努力も必要です。業界全体で排出量データの共有システムを構築する、取引先との長期的なパートナーシップを築くなど複数の企業が協力して削減策を検討していく必要があります。
③消費・経営自体が環境保護と矛盾することもある
脱炭素経営は企業活動の本質である「消費を促す」と、環境保護が目指す「資源消費を抑える」の間に本質的な矛盾を抱えていることもあります。
たとえば、2024年に開催されたパリオリンピックが挙げられます。パリオリンピックでは、会場建設での再設計、再生可能エネルギーの活用(98.4%電力を太陽光・風力で賄う方式)、再生資材の活用などを徹底して、ロンドン(2012年)・リオ(2016年)と比べてCO2排出量を54.6%削減しました。(参照1)
それでも、オリンピックとパラリンピックで排出したCO2の量は159万トンと発表されています。159万トンのCO2排出量は車で地球を182,675周する際の排出量と相当しており、環境専門家の中には消費活動・イベント活動の根本的な在り方自体にまで疑問を投げかける声もあがっています。
CO2排出量の数値を追うだけでなくビジネスモデルの変革を考えることも求められているといえるでしょう。



企業のサービスの質や価格だけでなく環境に与える影響も消費者によって、さらに厳しい目線でチェックされているわね
参照2:AP通信
合わせて読みたい記事:エコバッグはエコじゃない?実は環境負荷のあるもの6選
合わせて読みたい記事:グリーンウォッシュの実態とこれからー“サステナブル”の裏に潜む罠を知る
より本質的な環境への貢献を求められる時代へ
これまでの脱炭素経営はCO2排出量の数値を減らすことを重要視していました。
しかし、社会全体が環境問題への意識を高めるにつれ排出基準を超えないのはほとんど当たり前のようになってきており、現在は単なる数値目標の達成だけでなく、企業の事業活動が本当に社会や環境に貢献しているのかが求められています。
消費者の目線は厳しくなり、表面的な「エコ」だけでは評価されなくなるケースも少なくありません。ここでは、時代の変化と、それに伴う企業の新たな課題について解説します。
消費者からより徹底した環境配慮が求められる
現代の消費者は企業が提供する製品やサービスに対して、より徹底した環境配慮を求めるようになっています。実際、欧米では脱炭素や自社での環境への取り組みだけでなく、B Corp認証のような厳しい第三者の認証を受けられるレベルで企業が環境に貢献しているかを求められる例が増えています。
B Corp認証とは企業が環境保護、従業員への配慮、ガバナンスなど多岐にわたる項目で厳しい基準に満たしているかを証明する制度です。
中身があるのかないのかが消費者に見られているため、これからの時代は表面的なエコをアピールするだけでなく認証を取得できるような透明性の高い情報開示と本質的な環境貢献を行っていく必要があります。
合わせて読みたい記事:サステナブルな企業事例・国内外で環境貢献度の高い活動から学ぶ
「消費前提のビジネスモデル」からの転換
これからの時代は大量生産・大量消費を前提とした従来のビジネスモデルからの脱却も求められています。どれだけ省エネ化やCO2削減を進めても、消費活動が続く限り資源の枯渇や廃棄物問題など根本的な環境問題は解決しないからです。
長く使え、無駄な買い替えを生まない商品・サービスを設計したりイベントや事業活動の再設計を行ったりして、大量消費・大量動員ありきではなく資源循環や地域還元を前提にした仕組みを構築していかなくてはならないでしょう。
「あなたの会社が“環境に貢献する存在”と見なされるのは、どんなときか?」脱炭素の先にあるより複合的・長期的な経営モデルを考える必要があるのです。
私たち「地球未来図」では、脱炭素社会や再生可能エネルギーに関する知識をわかりやすく伝えるだけでなく、実際に行動に移すための選択肢も紹介しています。
運営元のレオフォースは、太陽光発電を生活に取り入れる人を増やすために、ピタエネという太陽光発電設置の相談や代理店サービスも展開しています。
「環境のために、まず何か始めたい」そんな方は、ぜひこちらの特集【ピタエネのひみつ】もご覧ください。
※本記事は「ピタエネ」を紹介するPRコンテンツを含みます。