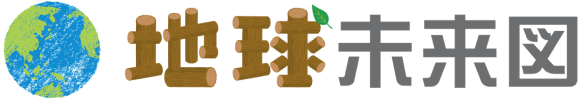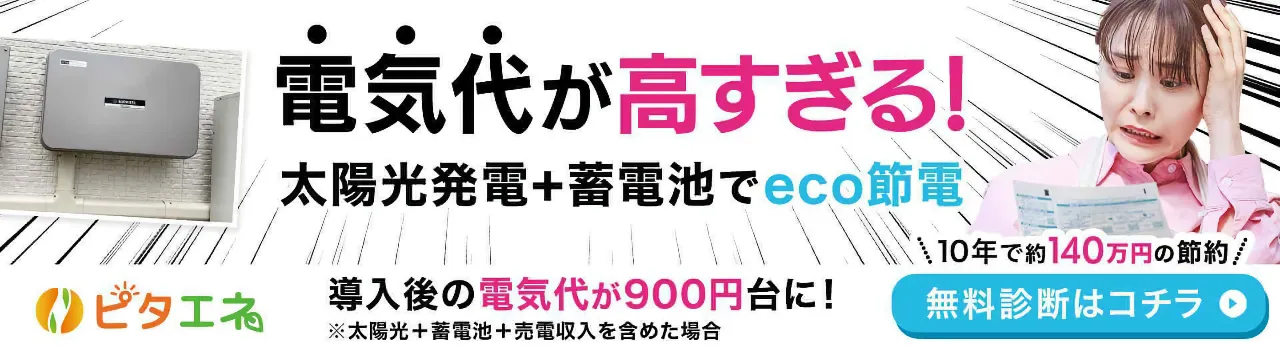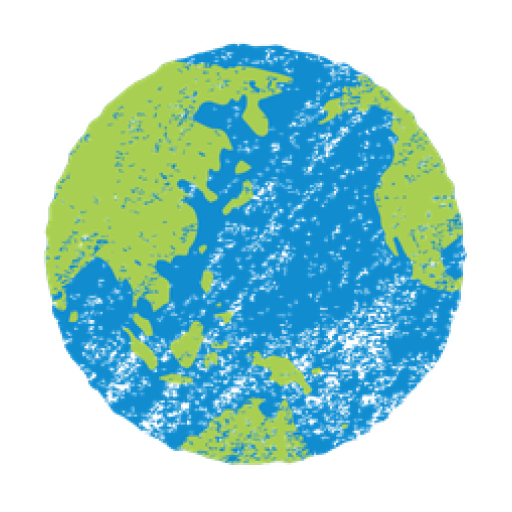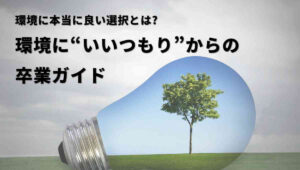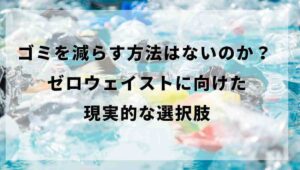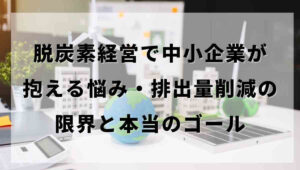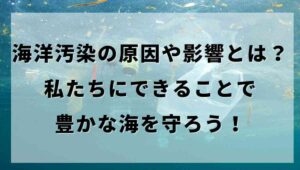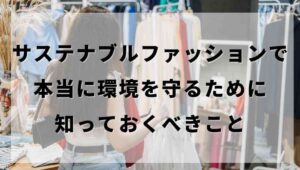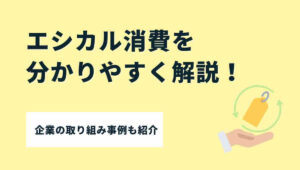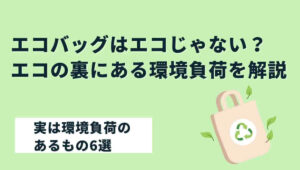SDGsブームから数年が経過し環境問題や社会課題への関心が高まる現代において、企業のサステナブルな活動は定着期に入ったといえるでしょう。しかし大手企業の事例ばかりが目立ち、中小企業や小規模なプロジェクト、日常的に企業が何をするべきなのかはあいまいだと感じているひともいるのではないでしょうか?
本記事では、サステナブルな企業についての理解を深めるために2025年の最新動向や中小企業の新しい取り組みを紹介します。これからの企業活動や消費行動を考えるヒントにしてください。
サステナブル企業とは何か
サステナブル企業とは、環境・社会・経済の3つの側面において持続可能性を追求した経営をしている企業のことです。短期的な利益を追求するだけでなく、事業活動を通じて環境保護や社会貢献にも積極的に取り組み、長期的な成長を目指しています。
2015年に国連でSDGs(持続可能な開発目標)が採択されたことで、サステナブルな社会を実現するための目標が明確化され、世界中でサステナブル経営に取り組む企業が増えてきました。また、サステナブルな企業に投資をするEGS投資が広まり、投資家の間でも注目が集まり始めました。
日本では2015年の国際的枠組み(SDGs・パリ協定)を契機に、投資家・規制・消費者の三方向からの圧力が強まり、2020年以降は脱炭素や資源循環などの取り組みを中心に「サステナブル経営」はほぼ必須条件になっています。
サステナブルな経営はSDGsの達成にも貢献するものであり、現代社会において企業が果たすべき重要な役割とされています。
合わせて読みたい記事:SDGsと脱炭素は関係あるの?それぞれの意味や役割を紹介
サステナブル企業がすべきこと
サステナブル企業を目指すには、ただ環境保護や社会貢献を目標として掲げるだけでなく、事業活動において具体的な行動を実践する必要があります。
たとえば、以下のような取り組みが挙げられます。
- 再生可能エネルギーを導入してCO2排出量を削減する
- 資源を有効活用するためのリサイクルシステムを構築する
- 従業員の労働環境を改善して働きやすい環境を整備する
- 従業員の多様性を尊重する
サステナブル企業は利益を追求しつつ環境や社会に与える悪影響を最小限に抑えることで企業価値を高め、長期的な成長へとつなげます。この考え方はCSR(企業の社会的責任)やSDGsとも関連しますが、少し違いがあります。
CSRが企業の社会貢献活動を指すことが多いのに対し、サステナブル企業は事業活動そのものに社会や環境への配慮を組み込む点が違いです。また、SDGsが世界共通の目標であるのに対し、サステナブルな経営は企業がその目標達成に向けてどのように取り組むかという具体的な戦略を指します。
合わせて読みたい記事:再生可能エネルギー国内・海外企業、自治体の取り組み事例10選
サステナブル企業:近年注目すべき国内事例
サステナブル経営を実践する企業は具体的な取り組みを通じて社会や環境に貢献し、企業価値を高めています。ここでは、独自のビジネスモデルや認証制度を活用して、持続可能な社会の実現に貢献している国内の注目すべき企業事例を3つのモデルに分けて紹介します。
環境に貢献できる商品を提供するモデル
サステナブルな経営に取り組む企業の中には、環境負荷を低減する商品を開発・提供することで、消費者や他の事業者と共に社会課題の解決を目指すモデルがあります。原貿易株式会社は、このモデルを実践する企業の一つです。サステナブルな製品であるリユーストナーカートリッジを販売しています。(参照1)
リユーストナーカートリッジとは、使用済みインクカートリッジの部品を一部だけ交換し作られた再利用可能な製品です。新しいカートリッジを製造するよりもCO2排出量とプラスチックの廃棄量を削減できます。また、純正品と比べて安価で購入できるため、企業の経費削減にも効果的です。
原貿易株式会社のリユーストナーカートリッジは環境保護と経済性の両立を実現しており、企業の持続可能性を高めています。
参照1:原貿易株式会社
合わせて読みたい記事:エコバッグはエコじゃない?実は環境負荷のあるもの6選
リユースのニーズに応えるモデル
近年、「ものを大切に長く使う」という意識が社会全体に広まってきており、リユースのニーズに応えるビジネスモデルを展開する企業が増えています。事例の一つとして株式会社カマンが挙げられます。
株式会社カマンは、地域共通のリユース容器シェアリングサービス「Megloo(メグルー)」を運営している企業です。Meglooはイベントや飲食店にリユース容器を提供しており、使い捨てプラスチックごみの削減とCO2排出量の削減に大きく貢献しています。
Meglooの容器は3回以上繰り返し使うだけで使い捨て容器よりもCO2排出量が下がり、100回繰り返し使用すると紙素材の使い捨て容器と比べてCO2排出量が90%も削減可能です。(参照2)
このモデルは環境意識の高い消費者や事業者のニーズに応えながら、地域全体のサステナビリティを高める取り組みとして注目されています。
参照2:Megloo
合わせて読みたい記事:エシカル消費とは?メリットや私たちにできることをわかりやすく解説
SBT認定を取得し、環境基準を守るモデル
国際的な環境基準であるSBT(Science Based Targets)認定を取得し、温室効果ガス排出量の削減に取り組むビジネスモデルも増加しています。
SBTとはパリ協定が求める「世界の気温上昇を産業革命前から2℃を十分に下回る水準に抑え、1.5℃に抑える努力をする」という目標のことです。世界中の企業がSBTに参加しており、2025年3月末時点で7469社がSBT認証を取得しています。そのうち、日本企業のSBT認定数は1479社でした。(参照3)
SBT認定には大企業を対象にした「SBT」と中小企業を対象にした「中小企業版SBT」があります。日本では中小企業SBTの認証を受ける企業が多く、2025年6月5日時点で1345社が認定を取得しました。(参照4)
SBT認定を取得することで、企業が設定するCO2排出削減目標がSBTにもとづいていると国際的な第三者機関に認められ、数値で測れる形での環境貢献ができます。
また、企業が気候変動対策に真剣に取り組んでいる証明となり、投資家や取引先からの評価向上にもつながります。
サステナブル企業:海外の事例
サステナブル経営は日本だけでなく世界中の企業でも推進されています。ここでは、特に注目すべき海外企業のサステナブルな取り組み事例を3つ紹介します。
メーカーの垣根を越えてパソコンを再製造する
パソコンは新しいモデルが次々と登場し、使用済みの機器が大量に廃棄されることで環境に大きな負荷をかけています。
この課題を解決するため、イギリスのCircular Computing社はメーカーの垣根を越えて使用済みノートパソコン(HP、Dell、Lenovoなど)を回収し、再製造(リマニュファクチュアリング)する独自のビジネスモデルを確立しました。
回収した使用済みノートパソコンを、5時間以上かかる独自の循環型再生プロセスと360項目の品質チェックにより新品同様の品質にまで引き上げてから再販売しています。新たな資源の採掘や製造に伴うCO2排出量を大幅に削減できるだけでなく、消費者が安心して再製造品を選べるようにしています。
合わせて読みたい記事:サーキュラーエコノミーの成功事例|日本と海外の最新取り組み6選
洋服を修理することを当たり前にする
ファッション業界では、大量生産・大量消費が環境にやさしくないと問題視されています。このような課題に対し、イギリスのスタートアップ「Sojo」はサステナブルなファッションを促進するユニークなサービスを提供しています。(参照6)
Sojoは2021年にイギリスではじまったサービスで、ユーザーがアプリを通じて修理を依頼すると専門の修理業者に洋服が集荷され、修理後に自宅へ届けられる仕組みです。
現在は個人からの修理だけでなく、Paul Smithなど有名ブランドの修理窓口も請け負うようになりました。「洋服を修理して長く着る」という簡単に思えても、手間や修理材料費が必要だったり、きれいに直すには技術が必要で、修理を断念している人も多いのではないでしょうか?
Sojoのようなサービスは、修理の申し込みがより簡単になり、修理後も長く洋服を使う習慣を広めるのに役立っています。
参照6:Sojo
合わせて読みたい記事:サステナブルファッションで本当に環境を守るために、知っておくべきこと
B Corp認証による環境で消費者への透明性を保つ
近年、欧米でB Corp認証が注目されています。B Corp認証とは企業が社会や環境に配慮した経営を行っていることを証明する国際的な制度です。
B Corp認証は企業が環境保護、従業員への配慮、ガバナンスなど多岐にわたる項目で厳しい基準をクリアしていることを示します。
 お客様
お客様SBT認定とは何が違うの?



SBT認定は基礎的な環境貢献を証明する制度です。温室効果ガス排出量の数値報告を義務付けており、投資家や社会に対するアピールに活用できます。
一方で、B Corpの認定基準はSBTよりも厳しく複雑です。3年ごとの再調査もあり、消費者が企業を判断する際の強い材料となります。
B Corp認証は企業の社会的責任を問うのに対し、SBT認証は気候変動対策の具体的な目標と実行性に焦点を当てています



SBT認証は環境問題に特化しているのね
B Corp認証はアメリカ発の制度ですが、欧州のブランドも積極的に認証を取得しています。日本では認証を取得している企業が2025年9月時点で62社とSBT認証と比較して少ないのが現状です。(参照7)
参照7:B Lab
まとめ:サステナブル企業の成功要因とは
サステナブル企業とは、利益だけでなく環境や社会への貢献を事業活動に組み込むことで長期的な成長を目指す企業のことです。
国内外の事例から見るとサステナブルな経営を成功させるには、以下の点が重要であると考えられます。
- 短期の数値にこだわって無理をするのではなく、長期的な目線で取り組む
- 地域の消費者や事業者と協力してサステナブルな取り組みを促進する
- B Corp認証やSBT認証などの国際的な認証を取得して企業の透明性を保つ
これから企業が持続的に発展していくためには、国内外の成功事例を参考にして社会や環境への貢献と企業の利益を両立していくことが不可欠であるといえるでしょう。また、持続可能な社会を実現するには、私たち消費者もサステナブルな取り組みについて正しく理解し、行動を変えていくことが大切です。
私たち「地球未来図」では、脱炭素社会や再生可能エネルギーに関する知識をわかりやすく伝えるだけでなく、実際に行動に移すための選択肢も紹介しています。
運営元のレオフォースは、太陽光発電を生活に取り入れる人を増やすために、ピタエネという太陽光発電設置の相談や代理店サービスも展開しています。
「環境のために、まず何か始めたい」そんな方は、ぜひこちらの特集【ピタエネのひみつ】もご覧ください。
※本記事は「ピタエネ」を紹介するPRコンテンツを含みます。