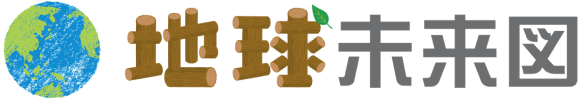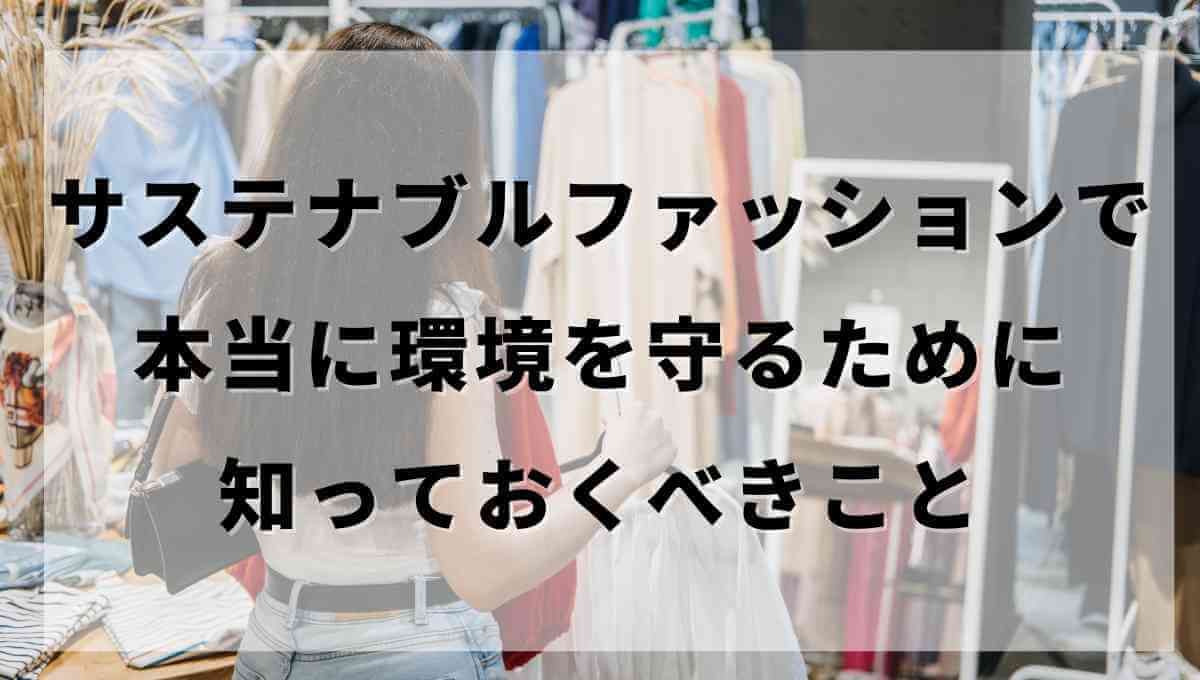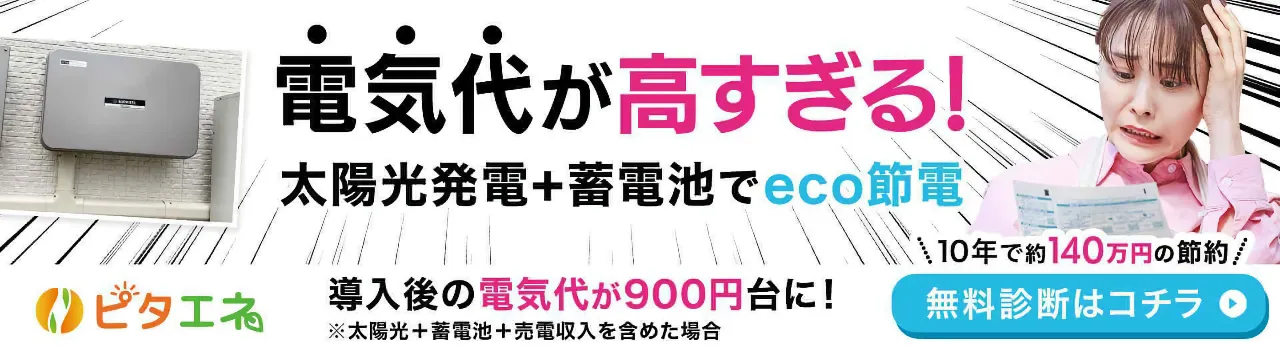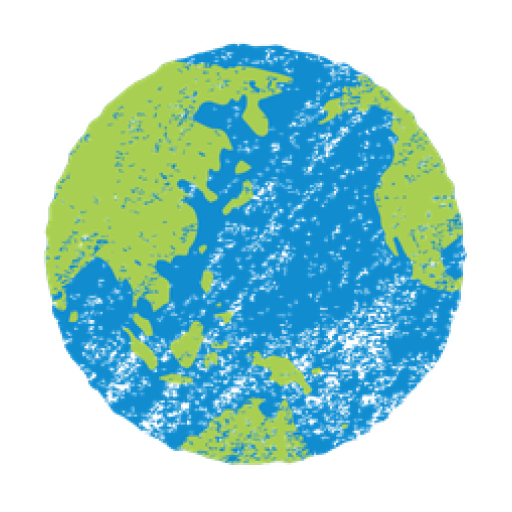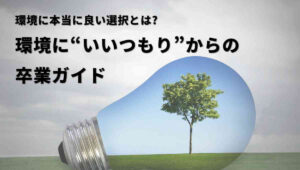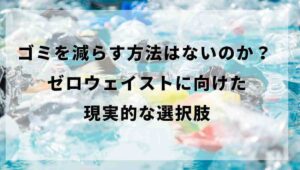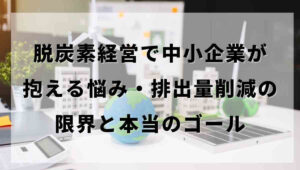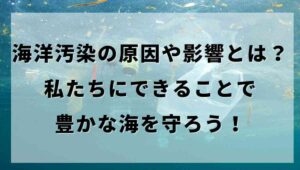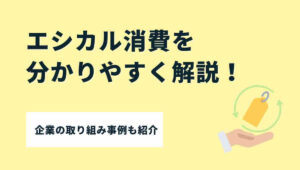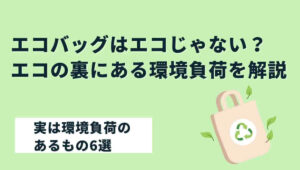最近「サステナブル」という言葉をよく耳するという方も多いのではないでしょうか。ファッション業界でも、サステナブルという言葉が使われることが増えてきました。
しかし「何が具体的にサステナブルなのかよく分からない」と感じているという意見もよく聞きます。また、実際にはサステナブル(環境に優しいアイテム)と謳っていても、別の問題を引き起こしているケースもあります。
この記事では、ファッション業界におけるサステナブルである「サステナブルファッション」について詳しく解説します。近年のファッション業界の矛盾点や、世界でのサステナブルファッションへの取り組みについて知識を深められる内容となっているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。
 地球未来図
地球未来図この記事を読むことで、一人の消費者として、ファッション業界に携わるビジネスマンとして知っておくべき現状や課題がわかります。ぜひ、この記事を読んでサステナブルファッションを支援する選択をしてみてくださいね。
サステナブルファッションの意味と定義
サステナブルファッションとは、洋服を作って捨てるまでの流れを環境だけではなく、労働者、社会にとってより良い方法で行っていくという考え方です。サステナブルファッションは、2010年代頃から世界的に注目されるようになりました。
「サステナブルファッション」と聞くと、環境に優しいオーガニック素材でエコな洋服を作るというイメージを持つ人もいるのではないでしょうか。しかし、実際にはエコな素材で洋服を作ることだけがサステナブルファッションではありません。
サステナブルファッションには、はっきりした定義や具体的な基準は存在しません。しかし、より環境や洋服を作る労働者、社会にとって優しいファッション業界を作るためには、サステナブルファッションの考え方をより深く理解し、実行していく必要があります。
サステナブルファッションが注目されている理由は、洋服の生産と廃棄による環境へのダメージが問題となっているからです。洋服を作るときには大量の水や電気などのエネルギーを必要とします。大量の水とエネルギーで作られた洋服は、流行が過ぎると大量に廃棄されているのです。
さらに、洋服を作る労働者の働き方にも問題があると指摘があります。このように、ファッション業界でサステナブルファッションを当たり前にしていくには、まだまだ課題が多いと言わざるを得ないのが現状です。
合わせて読みたい記事:グリーンウォッシュの実態とこれからー“サステナブル”の裏に潜む罠を知る
ファッション業界と環境保護の大きな矛盾
サステナブルファッションが注目される前から、ファッション業界の矛盾は問題視されていました。しかし、それはファッション業界でビジネスを行う企業だけが悪いわけではありません。
ファッション業界の矛盾を取り除き、より環境に優しいビジネスを行っていくためには、ビジネス業界全体や社会、洋服を購入する人全てが在り方を見直す必要があります。サステナブルファッションが注目されている近年、ファッション業界の矛盾について誰もが深く見つめ直している途中だといえるでしょう。
①年間15億点の衣料品が一度も着られず廃棄される
年間で販売される洋服の数は、おおよそ29億点だと言われています。その29億点のうち、消費(販売)されるのはおよそ14億点です。(参照1)つまり、年間で約15億点もの衣料品が一度も着られることなく廃棄されている計算になります。
もちろん、廃棄される洋服の全てがゴミに出されるわけではありません。日本国内で2022年度に廃棄された洋服の3.5万トンのうち、リサイクル・リユースされた衣料品は2.2万トンです。(参照2)
リサイクルされている衣料品があると言っても、年間1万トンの衣料品が廃棄されています。
もちろん洋服の廃棄は日本だけの問題ではなく、先進経済国のほとんどで同様の問題が見られます。
では、なぜ衣料品がこんなにも多く廃棄されてしまうのでしょうか。
衣料品が大量に廃棄される背景には、下記のような理由があります。
- 売り上げを増やすには、常に最新のデザインに入れ替える必要があるため
- 値下げ率や量をふやすと、定価の服を買う人が減るため
- 利益を出すために大量の洋服を販売しなければいけないため
このように、トレンドを追うファッション業界の特性上、衣料品の廃棄量が多くなってしまうのです。
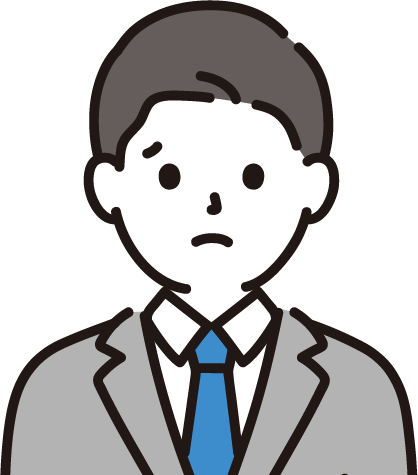
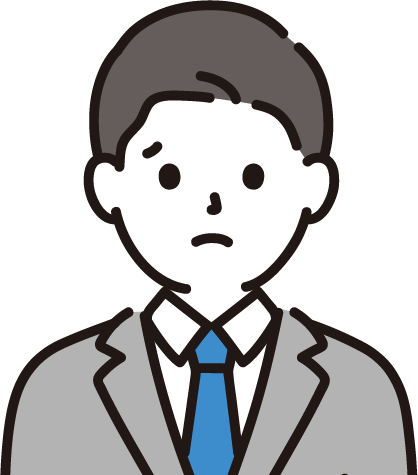
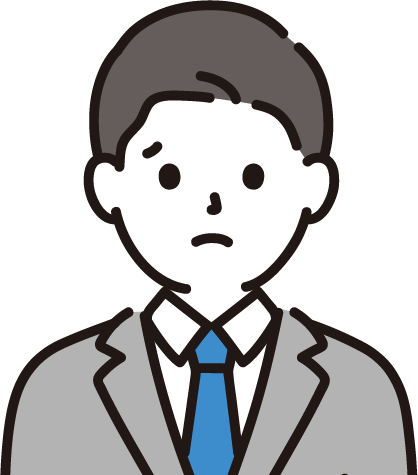
実は、以前にアパレル在庫処理の業務を行ったことがあります。どのように廃棄するかというと、廃棄される洋服をハサミで切り裂きます。こうして、転売や値下げができないように、販売できない状態にするのです。
一度も着られていない洋服を切り刻むのは、心が痛みました。
現在、フランスでは、洋服の焼却処分禁止という厳しい法律ができています。現在日本でも「未使用品の洋服の焼却はよくない」という方針を打ち出していますが、具体的に規制するまでには至っていません。
今後、衣料品の廃棄を減らすための解決策が必要になります。ブランドの利益を確保し、廃棄も減らす解決策が必要になるでしょう。
参照1:商業界オンライン :小島健輔氏論文より
参照2:消費者庁
合わせて読みたい記事:グリーントランスフォーメーション(GX)事例|日本と海外の最新取り組みを紹介
②Tシャツ1枚をつくるのに、約2,300リットルの水が使われる
Tシャツを1枚に必要な綿を作ったり、染色したりするために約2,300リットルの水が必要という概算があります。2,300リットルの水は、浴槽約11杯分です。(参照3)Tシャツ1枚を製造するのに、これほど大量の水を使っていることに、驚く人も多いのではないでしょうか。
最近は1枚1,000円ほどのTシャツなど、低価格で売られている洋服も多いです。低価格の洋服は「安くてありがたい」と思い購入する人も多いのではないでしょうか。しかし、実際には安い製品ほど、水資源や化学薬品を多く使用し、環境に影響がある方法で作られている可能性が高いのです。
今後、サステナブルファッションを普及していくとなると、洋服の値段が高くなる可能性もあります。安い洋服を購入して、環境への負荷に目をつぶるのではなく、高くても環境に優しい商品を購入者が選んでいかなければいけないのです。



洋服を作るのに水や電気がたくさん使われているのは知らなかったわ・・。



そうですよね。このように、大量の水や電気を使って作られた洋服が、毎年大量に廃棄されています。今後は、サステナブルファッションを徹底し、環境に優しい方法で作られた洋服が、なるべく廃棄されないアパレル業界の仕組みづくりが望まれています。
参照3:環境省_サステナブルファッション
合わせて読みたい記事:エコバッグはエコじゃない?実は環境負荷のあるもの6選
③月給1万円の労働環境で作られる
サステナブルファッションを実現するためには、洋服を作る人への配慮も必要です。いくら環境に優しい素材や工程で作られていても、生産者への賃金が低すぎたり、労働環境が悪かったりしたら、労働者に配慮した生産方法とは言えませんよね。
現在、衣類の多くはバングラディッシュやベトナム、カンボジアなどの発展途上国で作られているケースが多いです。価格が安いファストファッションは、最低賃金を下回る賃金で作られているケースもあります。
例えば、バングラディッシュの最低月給は2023年時点で約1万6,250円です。(参照4)対して、縫製工の1枚あたりの工賃は10円から20円程度です。衣料品を生産する人々が生活できる賃金を受け取るためには、今よりも5倍から10倍多い賃金の支払いが必要だと言われています。
当然、賃金の支払いが上がれば、衣料品の小売り価格も高くなります。労働者にフェアな賃金を支払うためには、Tシャツ1枚であれば30%から50%の価格上乗せが必要です。



30%から50%の値上げって、結構大打撃だわ・・。でも、今までの洋服が安すぎたってことよね。



そうですね。サステナブルファッションを実現し、労働者にも配慮した衣料品の生産をするためには、洋服の値上げは避けられません。
洋服を購入する消費者も、購入する洋服がどのように作られているのかを知り、ただ安いものを購入するという選択を考え直さなければいけませんね。



高くても、長く使えるのであれば、トータルでは家計にやさしいかもしれないわね
参照4:Jetro
合わせて読みたい記事:エシカル消費とは?メリットや私たちにできることをわかりやすく解説
現在すすめられているサステナブルファッションの取り組み
環境への負担や労働問題、廃棄問題を受けて、世界各地でサステナブルファッションへの取り組みが行われています。次の項目では、海外の動きに加え、日本の現状について解説していきます。
①海外の動き
サステナブルファッションに関する海外の動きとして、「サーキュラー・テキスタイル戦略」と「エクステンデッド・プロデューサー・レスポンシビリティ(EPR)」があります。
それぞれサステナブルファッションを実現する取り組みとして、世界中から注目されています。
EUの循環型経済政策「サーキュラー・テキスタイル戦略」
「サーキュラー・テキスタイル戦略」は、欧州委員会がビジネスと環境保護の両立を目指し、消費者の権利強化を目的として制定されました。ファッション業界(繊維戦略)においては、繊維の再利用を促し、循環型の環境に優しい市場を目指しています。
「サーキュラー・テキスタイル戦略」は、下記の5つの目標をEU内で販売される繊維製品を作る会社の行動指針としています。
- 寿命が長い
- リサイクルできる
- 再生繊維の活用
- 有害物質を含まない
- 労働者や環境に配慮している
この5つの目標をクリアした製品を販売することで、よりサステナブルで循環型のファッション業界を実現することが目的です。
英国の衣料廃棄対策と「エクステンデッド・プロデューサー・レスポンシビリティ(EPR)」制度構想
「エクステンデッド・プロデューサー・レスポンシビリティ(EPR)」は、ブランドや繊維製造業者に対して商品の廃棄に対する責任を持たせるために取り決めされました。事業者は、商品を販売するごとにエコ貢献金を支払います。
エコ貢献金の基準は、環境負荷の高さによって決まります。また、リサイクル繊維の含有量や修理のしやすさなどの基準が含まれ、サステナブルな商品であるほどエコ貢献金が安く設定されていることが特徴です。
英国では「エクステンデッド・プロデューサー・レスポンシビリティ(EPR)」を義務付けることにより、よりサステナブルファッションが当たり前になるような市場を目指しています。
②日本の現状:
海外と同様に、日本でもサステナブルファッションへの取り組みが行われています。日本政府は、サステナブルファッションを推進するためのプロジェクトを立ち上げました。プロジェクトでは、具体的な方針が明記されており、企業向け、消費者向けそれぞれに対して情報発信を行っています。
日本政府以外にも、自治体や企業による古着回収とリサイクルの実施や、オーガニックコットンのリサイクル、商品の生産によるCO2排出量などを消費者に見える化する取り組みなどが行われています。
ただし、日本にはEUや英国のようにサステナブルファッションに関する法律はまだありません。現在日本や企業が行っている取り組みでは、サステナブルファッションを普及させるために不十分だという意見もあります。
今後、日本にサステナブルファッションが普及するためには、日本政府だけではなく、ファッションブランドなどの企業、消費者が一丸となって問題に取り組む必要があると言えるでしょう。
合わせて読みたい記事:アップサイクルの現状・事例から問題点と可能性を考える
サステナブルファッションに私たちはどう向きあうのか?
サステナブルファッションを当たり前にするためには、企業だけではなく消費者の協力も必要です。私たち消費者ができることは、長く使えて、サステナブルに関する取り組みを行っているブランドの洋服を購入すること、レンタルの利用や、アップサイクル商品の購入などです。
さらに、企業ができることは消費者にも分かりやすいよう、サステナブルへ対する取り組みの見える化を徹底すること、洋服レンタルなどのビジネスの可能性を模索すること、廃棄をゼロにする製造・在庫管理の仕組みづくりなどです。
環境や労働者にも優しいサステナブルファッションを当たり前にするためには、消費者と企業など社会全体がひとつひとつの選択を変えていかなければいけません。
私たち「地球未来図」では、“これからの環境問題”に向き合うための情報として、脱炭素・ネイチャーポジティブ、そして太陽光発電の知識をわかりやすく紹介しています。
太陽光発電は、環境にやさしいだけでなく、電気代の削減や補助金の活用といった、家計にもメリットのある選択肢です。
「環境にいいこと、何か始めてみたい」 そんな方は、ぜひこちらの記事【ピタエネのひみつ】をのぞいてみてください。